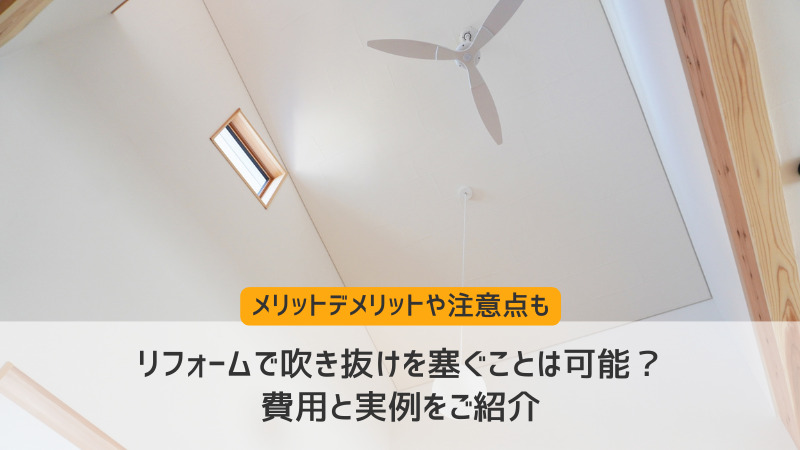
吹き抜けの明るく広々とした空間は魅力的ですが、一方で「冬に底冷えする」「家中に音が響いて落ち着かない」「手が届かず掃除が大変」といった、居住性に関する悩みや不満の声も多く聞かれます。
開放的な暮らしにあこがれて設置した吹き抜けが、いつしか悩みの種になってしまったとき、「いっそのこと吹き抜けを塞いでしまおうか…」とお考えの方もいらっしゃると思います。
この記事では、リフォームで吹き抜けを塞ぐことは可能なのか、塞ぐにはどのような方法があるのか、そして吹き抜けを塞ぐことのメリット・デメリットについて詳しく解説します。注意点や費用相場、吹き抜けを塞いだ実例まで、さまざまな情報も併せてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
リフォームで吹き抜けを塞ぐことは可能?
結論から言うと、リフォームで吹き抜けを塞ぐことは可能です。
実際に、リフォームで吹き抜けを塞ぐ工事を選択される方は少なくありません。「大がかりな工事になりそうで不安…」と感じる方もいるかもしれません。しかし、工事の内容をしっかり検討し、必要な条件を満たせば、吹き抜けを塞ぐことは十分に実現可能です。
ただし、吹き抜けを塞ぐことは単に空間を仕切るだけでなく、人が歩ける床を新設することになります。そのため、主に防災上の観点から建物の法規に関わる注意点があります。素人が安易に判断することは危険ですので、信頼できるプロに相談しましょう。
吹き抜けの問題点と解消する方法
吹き抜けには家中が一体となった開放的な暮らしを実現できる魅力がある一方で、特有の問題点も存在します。まずは、吹き抜けにはどのような問題があるのかを見ていきましょう。
吹き抜けの問題点
冬に室内が寒い
吹き抜けの最も大きな問題点として挙げられるのが「冬の寒さ」です。
暖かい空気は上昇し、冷たい空気は下降する性質があります。吹き抜けがあると、暖房で暖められた空気が上部の空間に逃げてしまい、生活空間ががなかなか暖まりません。特に、採光のために大きな窓やトップライト(天窓)が設置されている場合は、窓からの冷気も下降し、さらに寒くなってしまうこともあります。
大きな空間を暖める必要があるうえに冷気の下降で暖房効率が悪くなり、光熱費がかさんでしまう原因にもなってしまうのです。
生活音が響く
吹き抜けは上下の階がつながった大きな空間になっているため、音が家全体に響きやすいという欠点があり、下の階のテレビの音や話し声、台所での料理や洗濯機の音などが上の階に伝わりやすくなります。
反対に、上の階の子どもの足音や物が落ちる音などが、下の階に大きく響くこともあります。
家族の間であっても、プライベートな空間を確保するのが難しくなったり、音が気になって落ち着けなかったりして、ストレスを感じる人もいらっしゃるでしょう。
転落の危険
吹き抜けの周りの手すりや腰壁は、小さなお子様やペットがいるご家庭では、転落の危険性があります。
手すりの高さや強度が不十分だったり、デザインによっては隙間が大きかったりすると、予期せぬ事故につながる可能性があります。また、物を落とした際に、下の階にいる人に当たってしまう危険性も考えられます。
掃除が大変
吹き抜けの高い場所にある窓や照明、シーリングファン、天井の梁などに溜まったホコリは、掃除が非常に困難です。
脚立を使っても手が届かない場合が多く、専門の清掃業者に依頼せざるを得ないこともあります。
吹き抜けの問題を解消する方法
これらの吹き抜けの問題点を解消する一般的な方法についてご紹介します。
シーリングファンやサーキュレーターを設置する
吹き抜けの寒さ対策としては、まずシーリングファンやサーキュレーターを設置することが考えられます。これらの機器は空気を循環させることで、天井付近に溜まりがちな暖かい空気を下の階に送り、上下階の温度差を減らすのに役立ちます。
その結果暖房効率が上がり、光熱費の節約につながる可能性があります。ただし、設置には天井の補強や電気工事が必要となる場合があるため注意が必要です。
また、これらの対策は一時的なものであり根本的な寒さの解決には至らないことや、音の問題や転落のリスクは解消されないことを理解しておく必要があります。
高窓やトップライト(天窓)を断熱化する
吹き抜けが寒い大きな原因の一つは、窓から熱が出入りしやすいことです。特に、高い位置にある窓やトップライト(天窓)が大きい場合、または窓の断熱性能が低い場合は、冬に冷たい空気が入りやすく、夏には強い日差しで室温が上がってしまいます。
そこで、窓を断熱性の高い複層ガラスやトリプルガラスに交換したり、内窓を取り付けたり、断熱フィルムを貼ったりすることで、窓の断熱性能を高めることができます。これにより、冷暖房の効果が上がり、室内の温度を快適に保つことが期待できます。
DIYで簡易的に吹き抜けを塞ぐ
費用を抑えたい場合は、ご自身でDIYによって簡単に吹き抜けを塞ぐ方法も検討できます。例えば、梁に布を取り付けたり、簡易的なパネルを設置したりするなどの方法です。
ただし、これらは一時的な対策であり、根本的な寒さや音の問題を解決するには不十分なことが多いでしょう。さらに、安全面にも注意が必要です。吹き抜けに身を乗り出したり、不安定な脚立上で作業をすることになりますので、転落しないよう十分に気を付けましょう。
プロに依頼して完全に塞ぐ
寒さ、音、安全性の問題をしっかりと解決したい場合は、リフォーム業者に依頼して吹き抜けに床を設置し、完全に塞ぐのが一番確実な方法です。
吹き抜けだった場所に床と壁を作ることで、上下の階を完全に分けられます。また、床で塞いだ部分を部屋や収納として活用することもできます。
吹き抜けを塞ぐメリット・デメリットと注意点
吹き抜けを塞ぐリフォームで多くのメリットが得られる可能性がある一方で、デメリットや注意すべき点も存在することに注意しなければなりません。
吹き抜けを塞ぐメリット
空調効率が上がり室内が暖まりやすくなる
吹き抜けを塞ぐことで、暖房や冷房の効きが非常に良くなる可能性があります。暖めた空気や冷やした空気が広い空間に逃げることがなくなり、部屋全体が効率よく暖かく、または涼しくなるからです。
特に冬の「寒すぎる」という悩みは大きく解消されるでしょう。その結果、電気代などの光熱費を抑えることにもつながります。
生活音が室内に響きにくい
吹き抜けを塞いだ結果、新しく床と壁ができると、上の階と下の階で音が響きにくくなります。例えば、1階のテレビの音や話し声が2階に聞こえにくくなったり、2階の足音や物が落ちる音が1階に響きにくくなったりします。
家族の中で生活時間が違う場合や、二世帯住宅のように別々の世帯が住んでいる場合など、家族間でのプライベートな空間を大切にしたい時にはとても助かるでしょう。
床にすれば生活スペースが広がる
吹き抜けを塞いで床を新しく作ることで家の中に使えるスペースが広がり、部屋を増やしたような効果が得られます。これは、家の外にスペースを足す「増築」とは違いますが、家の中で自由に使える場所が増えるという点で、増築と似たメリットがあります。
たとえば、お子さんの部屋、書斎、趣味の部屋、または大きな収納スペース(納戸やウォークインクローゼット)など、家族の人数や暮らし方の変化に合わせて、今まで足りなかった部屋を作ることができます。今の家の広さのままで、住む場所や収納を増やせるのは、とても嬉しいポイントです。
耐震性能を上げることも可能
吹き抜けを塞いで床を新しく作ることで、家を地震に強くすることにつながる場合があります。吹き抜けがある家は、構造上、横からの力に対する強さ(水平剛性)が弱くなりがちです。この水平剛性とは、建物が地震で揺れたときに、建物がねじれたり変形したりするのを防ぐ力のことです。
吹き抜けにしっかりと床を組み込み、家の構造と一体化させることで、この水平剛性を高めることができます。つまり、地震が起きたときに建物が壊れにくくなる効果が期待できるのです。
ただし、どのような方法で床を作るかによって効果は変わるので、専門家によるしっかりとした設計と工事が重要です。
吹き抜けを塞ぐデメリット
室内の解放感が無くなり暗くなる
吹き抜けを塞ぐと、一番の魅力だった開放的な空間はなくなってしまいます。さらに、吹き抜けを通して2階から入っていた自然光が遮られるので、特に1階が今までよりも暗くなるかもしれません。
そのため、照明配置や台数を見直したり、壁紙などを明るい色にしたりする工夫が必要になることもあります。
リフォーム費用が掛かる
吹き抜けを塞ぐリフォームでは、床や壁を新しく作ったり、必要に応じて照明やコンセントを増やす電気工事も必要になります。工事中は作業用の足場を組む必要があり、普段通りの生活をしながら工事を進めるのが難しい場合もあります。そのため、ご自身でDIYするのとは違い、ある程度の費用がかかることを考えておく必要があります。
費用の相場は15~100万円程度と、工事の大きさや内容、使う材料によって大きく変わります。
リフォームで吹き抜けを塞ぐ際の注意点
安易にリフォームすると違法建築になってしまう
リフォームで吹き抜けを塞いで床を作る行為は、建築基準法上「増床」とみなされます。そのため、家全体の床面積が増えることになり、主に防災の観点から法律で定められた様々な制限を確認する必要があります。
特に重要なのが「建築確認申請」の手続きです。ご自身で勝手に工事を進めたり、専門知識のない業者に依頼したりすると、意図せず法律違反の建物になってしまう可能性があります。例えば、火災報知機などの防災設備が設置されていなかったり、緊急時の外部への避難経路が確保されていない部屋を作ってしまうケースなどが考えられます。
もし法律違反の建物になってしまうと、将来的に家を売却することが難しくなったり、行政からリフォームを元に戻すよう指導を受けたりするリスクがあります。
防火地域や10㎡を超える床面積などの場合は「建築確認申請」が必要
吹き抜けを塞ぐリフォームで「建築確認申請」が必要となる主なケースは以下の通りです。
- 防火地域・準防火地域内での増改築
都市計画で定められた防火地域や準防火地域内で増築を行う場合は、面積に関わらず建築確認申請が必要になります。 - 10㎡を超える増床
リフォームによって増える床面積が10㎡(約6畳)を超える場合は、建築確認申請が必要です。吹き抜けの面積がこれを超える場合は、申請が必要になる可能性が高いと考えましょう。
ただし、特例もあります。吹き抜けを塞いで新たに設けられたスペースが下記に該当する場合です。
- 天井高さ1.4m以下かつ直下階の床面積の1/2未満のロフトや収納スペース
つまり、人が長時間居ることのないスペース(非居室)の増床です。この場合は床面積に算入されず、建築確認申請が不要となる場合があります。
ただし、判断基準が自治体によって異なるため、必ず事前に専門家に確認するようにしましょう。
吹き抜けを塞ぐリフォームの実例と参考費用
実際に吹き抜けを塞ぐリフォームを実施した実例をご紹介します。
【130万円】家の吹き抜けをリフォームして埋めたらこう変わった!
※横にスクロールできます


【リフォーム概要】
- 建物形態:木造一戸建て
- 工事期間:10日間
- 工事費用:総額約130万円(その内、吹き抜けを塞ぐ工事は約50万円)
【お客様の悩み】
- 吹き抜けスペースが活用できていない
リビング上部の吹き抜け空間が活用できておらず、「もったいない」と感じていました。雨の日などに洗濯物を干せる室内干しスペースも欲しかったです。 - ロフトへのアクセスの悪さ
吹き抜けの上にあるロフトへは1階から高くて急なはしごでしかアクセスできず、扇風機や暖房器具、重いアウトドア用品などを運ぶのが大変で危険を感じていました。 - 冷暖房効率の悪さ
吹き抜けがあることで、冬場は暖房の暖かい空気が上へ逃げてしまい、1階が暖まりにくいことに不満がありました。
【リフォーム内容・効果】
メインの吹き抜け改修
※横にスクロールできます


1階の明るさをできる限り維持するため、床材には光を通すFRPグレーチング(※1)のクリア色を採用。これにより、吹き抜けを埋めても1階の明るさは以前とほとんど変わらず維持されました。
ロフトへのアクセス改善

2階廊下から直接ロフトへ入れるように動線を変更。荷物の出し入れの危険や手間がなくなりました。
ロフト内部の天井を一部解体し、中でまっすぐ立てる高さを確保。天井が高くなったことで使い勝手も格段に向上し、収納量も大幅にアップしました。
(※1)FRPグレーチング:繊維強化プラスチック製の格子状の板。軽くて丈夫、錆びないのが特徴。通常、マンションのバルコニーや工場の床などに使われることが多い素材。
上記はあくまで一例です。
吹き抜けを塞ぐリフォームの費用は、吹き抜けの面積、構造、新たに作る部屋の用途(ただ塞ぐだけか、居室として仕上げるか)、内装のグレード、電気工事の有無などによって大きく変動します。数十万円で可能なケースから、数百万円規模になるケースまで様々です。
リフォームガイドでは、厳選された優良リフォーム会社をご紹介しています。無料で手軽に相見積もりが取れますのでぜひご利用ください。
まとめ
この記事ではリフォームで吹き抜けを塞ぐことについての問題点と解決策、メリット・デメリット、実例などを解説しました。
吹き抜けがもたらす開放感は魅力的ですが、寒さや音、スペースの不足といった問題で悩んでいるのであれば、「吹き抜けを塞ぐ」という選択肢は、あなたの家の快適性と利便性を大きく向上させる可能性を秘めています。
ただし、法規的な側面や構造的な安全性を十分に考慮する必要があるため、信頼できるプロの意見を聞くことが不可欠です。リフォームガイドでは、お客様のリフォームに関するお悩みを解決し、より快適な住まいを実現するためのお手伝いをしています。ぜひお気軽にご相談ください。










 なら
なら

