【2026年の情報も】電気代の値上げは続く?今後の動向と有効な対策とは
ロシアのウクライナ侵攻などを背景に高騰が続いていた電気代も、ピークを過ぎて落ち着きをみせていますが、…

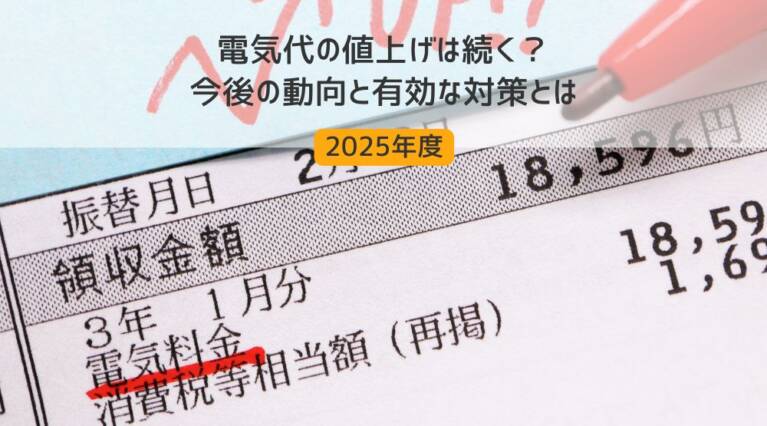
目的別リフォーム, 省エネリフォーム
ロシアのウクライナ侵攻などを背景に高騰が続いていた電気代も、ピークを過ぎて落ち着きをみせていますが、…
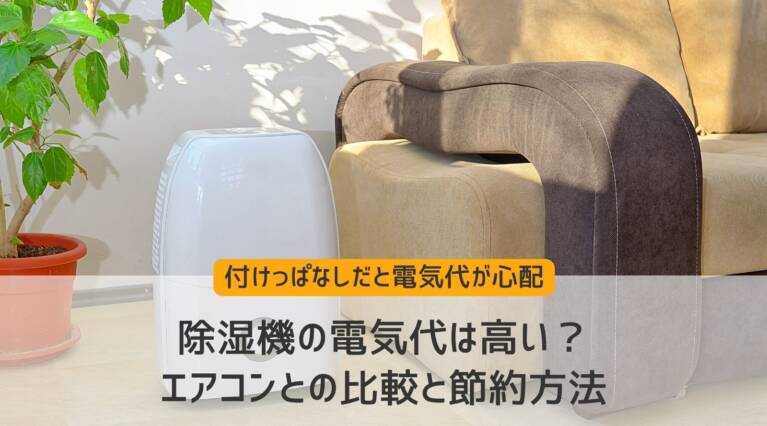
目的別リフォーム, 省エネリフォーム
室内干しが多くなる梅雨や雪の時期には、部屋の湿度を下げてくれる除湿機が大いに役立ちます。 一方…

目的別リフォーム, 省エネリフォーム
乾燥しやすい季節に、出番が増えるのが加湿器です。加湿器を長時間稼働させていたら、月の電気代が高くつい…
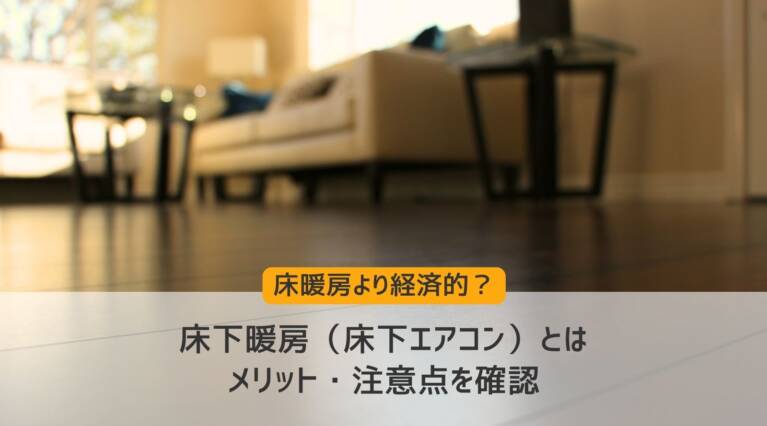
目的別リフォーム, 省エネリフォーム
寒い冬でも快適に過ごすため、住まいの暖房にはこだわりたいところです。近年、床下部分に暖房機器を設置し…
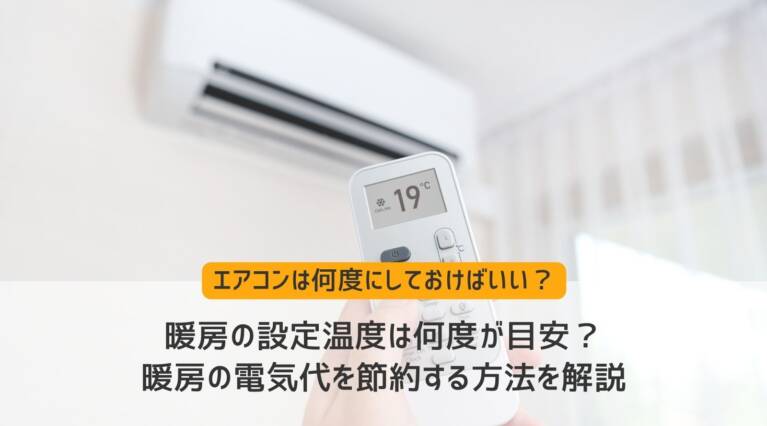
目的別リフォーム, 省エネリフォーム
冬は暖房を付けて快適に過ごしたいものですが、暖かさを保つために付けっぱなしにしておくと、気になるのが…

目的別リフォーム, 省エネリフォーム
家をリフォームして、月々の光熱費を安く抑えられたら嬉しいですよね。 近年は物価の高騰により、各家庭…
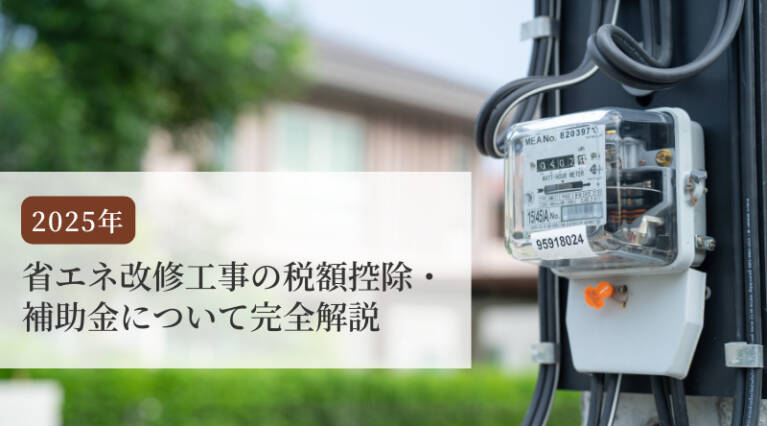
目的別リフォーム, 省エネリフォーム
自宅のリフォームで、断熱工事やエネルギー効率の高い機器や太陽光発電設備の導入といった省エネ改修工事を…
厳しい審査をくぐり抜けた優良リフォーム会社の中から、
プロのコンシェルジュがあなたにぴったりのリフォーム会社をご紹介!
有力候補・複数社の、お見積もりの手配を代行します!
厳しい審査をくぐり抜けた優良リフォーム会社の中から、プロのコンシェルジュがあなたにぴったりのリフォーム会社を選び、複数社のお見積もりの手配まで対応いたします!