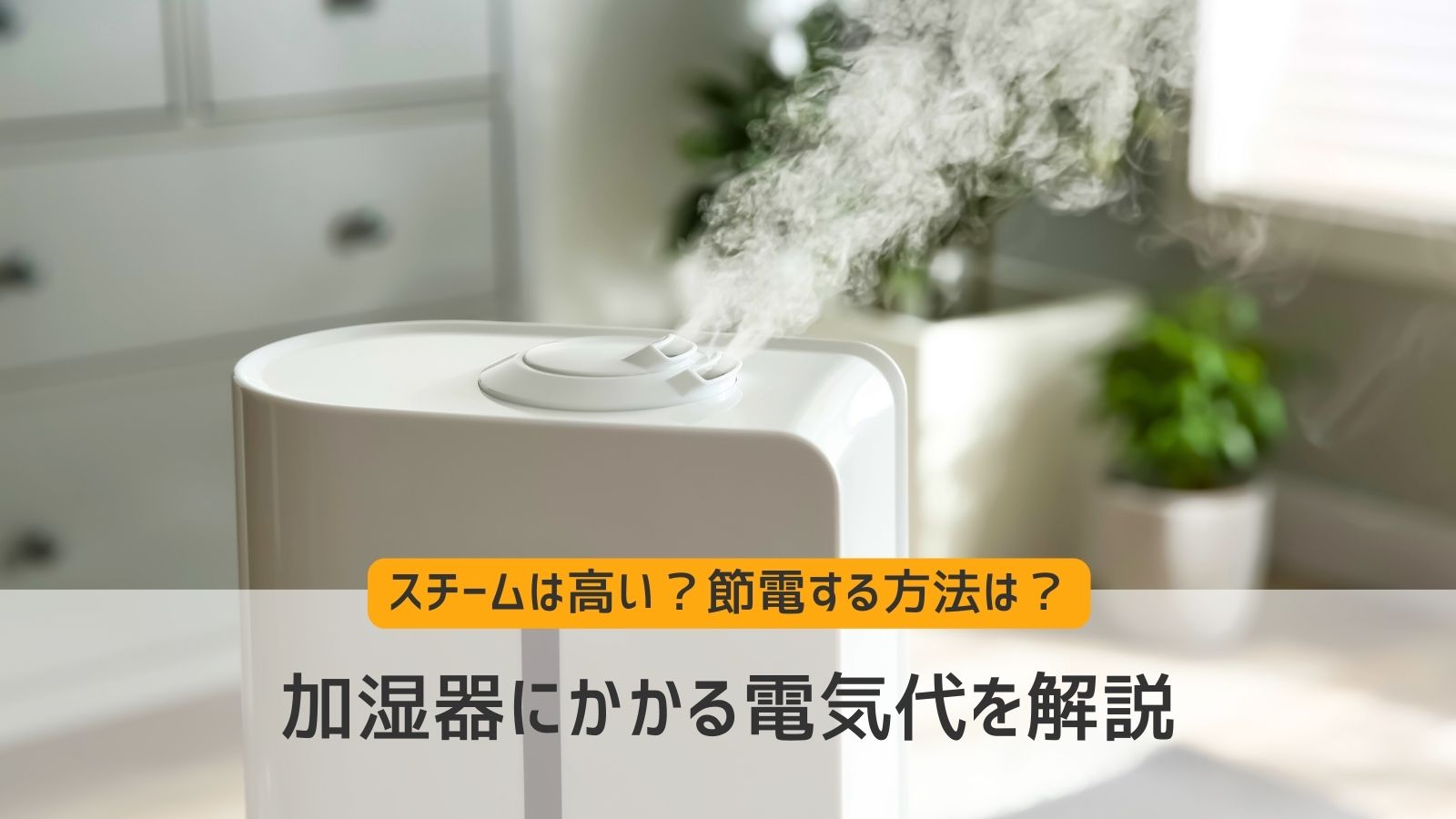
乾燥しやすい季節に、出番が増えるのが加湿器です。加湿器を長時間稼働させていたら、月の電気代が高くついてしまったという方は多いのではないでしょうか。もしくは、これから加湿器を購入するにあたって、なるべく電気代のかからないものを選びたいという方もいるでしょう。
今回は加湿器をテーマに、加湿器の種類ごとの特徴や電気代、選び方を解説します。また、加湿器を使いながら電気代を節約する方法や、加湿器を使わない加湿方法も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
1.加湿器の種類と電気代
加湿器には大きく分けて4つのタイプがあり、タイプごとに消費電力や電気代が異なります。各タイプの消費電力と電気代を表にまとめました。
| 加湿器の種類 | 消費電力 | 電気代/1時間 | 電気代/1ヶ月(30日) ※1日8時間使用した場合を想定 |
|---|---|---|---|
| 超音波式加湿器 | 22W〜30W | 0.6円~0.8円 | 144円~192円 |
| スチーム式加湿器 | 250W〜270W | 6.8円~7.3円 | 1,632円~1,752円 |
| 気化式加湿器 | 9W〜32W | 1.6円~7.2円 | 48円~216円 |
| ハイブリッド式加湿器 | 40W〜98W | 1.1円~2.6円 | 264円~624円 |
※5~6畳の部屋を想定 / 電気料金の単価27円/kWhを想定
それぞれの加湿器の仕組みと特徴を見ていきましょう。
2-1.超音波式|水を加熱しない点がメリットでデメリット

超音波式の加湿器は、超音波の振動を水面に伝えて細かな霧を発生させ、部屋を加湿する仕組みです。
水を加熱する必要がないため加湿器本体が熱くならず、部屋の温度が上昇する心配がありません。また本体が安い物が多く、電気代も比較的安価です。
一方で、霧の粒子が大きい分、壁紙やカーテンを湿らせてしまう恐れがあります。また、加熱しないことから、お手入れを怠るとタンク内にカビや雑菌が繁殖しやすいこともデメリットです。
2-2.スチーム式(加熱式)|パワフルだが電気代が高くなる
スチーム式は加熱式とも呼ばれ、ヒーターで水を加熱して蒸発させ、湯気(水蒸気)を発生させることで室内を加湿します。
湯気が温かく室内の温度を上げられるため、冬場の加湿におすすめです。大量の水蒸気が発生するので、広い部屋でも短時間で加湿することができます。しかし電気代が高く、また吹き出し口が高温になるため注意が必要です。
2-3.気化式|モーター音が出ることに注意
気化式の加湿器は、水を含ませたフィルターに風をあて、気化した水蒸気を放出して室内を加湿します。
水を加熱するヒーターがついていない分、電気代を抑えられます。また本体が加熱しないので、室温が上がることもありません。
一方でフィルターに風をあてる際にファンを稼働させるため、モーターの音が少々うるさい点がデメリットです。また、フィルターが常に湿っている状態になるので、カビが発生しやすい点にも注意しましょう。
2-4.ハイブリッド式(加熱気化式)|室内をすばやく加湿
ハイブリッド式は加熱気化式とも呼ばれ、気化式のように水を含ませたフィルターに風をあてて加湿する仕組みです。気化式と異なるのは、ヒーターで加熱した風をあてる点です。温風をあてる分、通常の気化式よりも早く水蒸気を発生させられ、室内をスピーディーに加湿できます。
しかし、ヒーターを使う分消費電力が大きく、電気代が高くなりがちな点がデメリットです。
2.加湿器の選び方
加湿器を選ぶ際は、電気代と加湿力のどちらを重視するか明確にしておくと良いでしょう。
2-1.電気代を重視するなら「超音波式」「気化式」
なるべく電気代を抑えたいのなら、「超音波式」「気化式」の加湿器がおすすめです。この2種類は「スチーム式」「ハイブリッド式」の加湿器に比べ消費電力が小さく、その分電気代も安い傾向にあります。
スチーム式やハイブリッド式に比べると加湿力が劣りますが、ベッドの周りやデスク周辺など、限られた空間を加湿するのではあれば十分です。
2-2.加湿力を重視するなら「スチーム式」や「ハイブリッド式」
加湿力を重視するのではあれば、大量の水蒸気を発生させる「スチーム式」やスピーディーに部屋を加湿できる「ハイブリッド式」がおすすめです。
スチーム式やハイブリッド式は消費電力が大きい分電気代が高くなりますが、広い部屋の加湿や乾燥が激しい室内の加湿にはぴったりです。多少電気代が高くなってもしっかり加湿したいという方に良いでしょう。
3.加湿器を使いながら電気代を節約する方法
乾燥する季節に加湿器を長時間稼働させることを考えると、電気代はなるべく抑えたいところです。加湿器を使いながら電気代を節約する方法を4つ見ていきましょう。
3-1.部屋の大きさにあった加湿器を選ぶ

加湿器を使用する際は、部屋の広さに合う機種を選ぶことが大切です。
例えば、広い部屋で加湿範囲の狭い加湿器をフル稼働させると、加湿力が追いつかないのに電気代が高くついてしまいます。加湿器にはそれぞれ使用に適した部屋の広さがあり、製品ごとに記載されています。加湿器の効果を効率よく最大限発揮させるには、部屋の広さに合った製品を選ぶようにしましょう。
3-2.エアコンの設定温度を下げる
冬場に暖房をつけながら加湿器を稼働させる際は、エアコンの設定温度を下げることをおすすめします。
人間の体は、乾燥した状態より体感湿度が高い状態の方が暖かく感じます。加湿器で体感湿度を上げて、その分暖房の設定温度を下げれば、エアコンの電気代を抑えられます。加湿器の電気代を節約するというよりも、加湿器+エアコンのトータルの電気代を抑えたい場合に有効です。
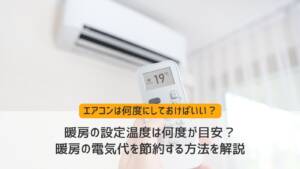
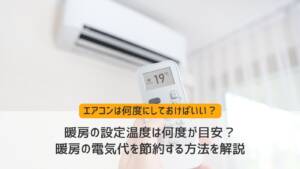
3-3.フィルター掃除をこまめに行う
フィルターに汚れが溜まって詰まり気味になると、加湿器に負荷がかかり、必要以上に電力を消費して稼働してしまいます。運動効率が下がり電気代も増えてしまうので、フィルターの掃除はこまめに行いましょう。
加湿器のフィルターの形状や素材によって、お手入れしやすさが異なります。また、除菌機能を備えた機種もあるので、購入前に確認しておきましょう。
3-4.加湿器を置く場所に注意する
加湿器を効率良く稼働させるには、置く場所も重要です。なるべく負荷のかからない場所に置けば、電気代を節約できます。以下の場所は避けましょう。
加湿器を置くのは避けたい場所
- 窓際:湿度が高いため、加湿センサーが反応して正常に稼働しなくなる
- キッチン付近:換気扇が水蒸気を吸ってしまう
- 床へ直置き:床は湿度が高い傾向にあるため、加湿センサーが反応して効率が落ちる
加湿器は、床から50cm~100㎝の高さに置くのがベストです。また、エアコンの下に設置すると、温風が水蒸気を部屋全体に運んでくれます。
4.加湿器を使用しない加湿方法
加湿器を使用しなくても、さまざまな方法で室内を加湿できます。
加湿器を持っていない、または電気代を考えて加湿器を使う時間を短くしたい方は、以下の方法を試してみてください。
4-1.濡れタオルや洗濯物を部屋に干す
濡れたタオルや洗濯物を室内に干せば、少しずつ水分が蒸発して空気中の水分量が増え、部屋の湿度を上げることができます。日当たりの良い窓際に干し、部屋干し用の洗剤や柔軟剤を使用すれば、臭いも気になりません。
4-2.浴室の扉をあけっぱなしにする
浴槽のお湯をためた状態で浴室の扉を開けておくと、浴槽内のお湯が蒸発して部屋を加湿することができます。加湿効果が高い反面、浴室の近くの壁にカビが発生しやすくなる点がデメリットです。
浴室の扉を開ける際は扇風機や換気扇を使い、水蒸気が室内にうまく行きわたるよう注意しましょう。
4-3.水を入れたコップを置く
コップに入れた水が蒸発するだけでも、加湿効果が期待できます。寝る前の枕元など、ポイントで加湿したい場合に良いでしょう。
水の温度が高いほど蒸発の際の水蒸気量が増えるので、冷水よりもお湯がおすすめです。
4-4.観葉植物を置く
観葉植物の葉にある気孔には、根から吸収した水分を空気中に蒸散させる役割があります。特に夏に蒸散が起こりやすいので、冷房時の加湿に有効です。また、観葉植物には加湿以外にも空気清浄効果やリラックス効果があります。
4-5.調湿機能を持つ素材に変える

調湿効果のある素材を内装に使うだけでも、加湿効果を得られます。
珪藻土や無垢材といった自然素材は、湿度が高すぎるときは吸湿し、乾燥時は吸湿した水分を排出します。電気を使わずに室内の湿度を適切に維持してくれるので、冬場だけでなく湿気の多い梅雨でも快適に過ごせます。
4-6.乾燥しにくい間取りにリフォームする

さまざまな方法を試しても乾燥が気になる場合は、リフォームをして根本から解決する方法がおすすめです。
室内が個室や廊下などで細かく分断されていると、湿度が高すぎる場所と乾燥する場所の二極に分かれてしまう傾向があります。湿気が溜まりやすい水回りを空気が循環しやすい間取りに変更する、乾燥しやすい空間に室内干し用のスペースをつくるなど、住まいに合ったリフォームを相談しましょう。
5.まとめ
加湿器には大きく分けて4つのタイプがあり、加湿の仕組みによって電気代が異なります。加湿力に優れ広範囲に使えるものは電気代が高い傾向にありますが、使い方を工夫することで電気代を抑えることが可能です。
加湿器を使ってもまだ乾燥が気になる場合は、乾燥しにくい間取りにリフォームする方法もおすすめです。根本の原因を解決できる分、電気代を節約できる可能性があります。
間取りリフォームの際は、住まいの状況をよく見て細かな提案をしてくれるリフォーム業者を選びましょう。リフォームガイドで、ぜひ信頼できるリフォーム業者を見つけてください。








 なら
なら

