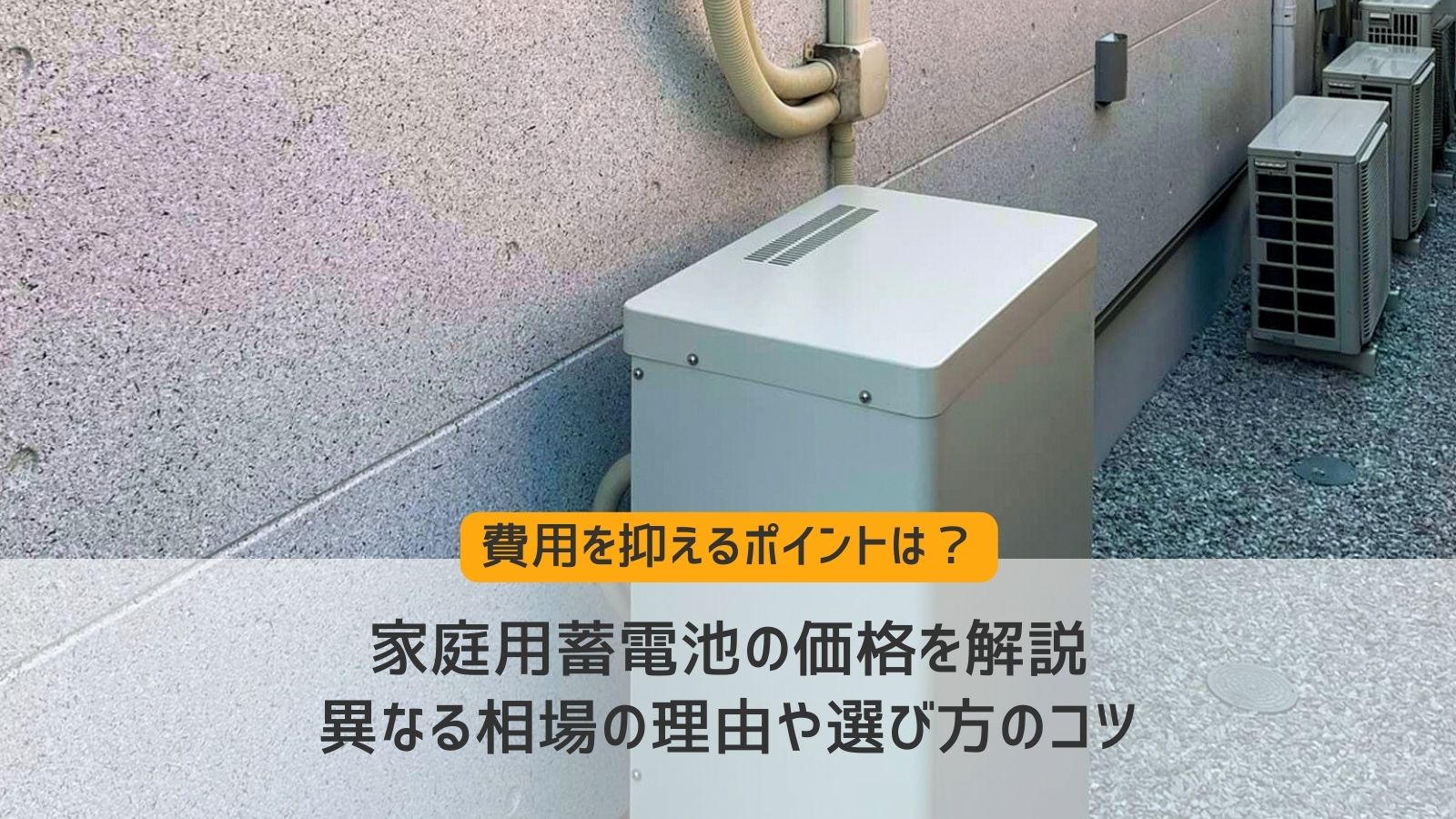
家庭用蓄電池はさまざまな種類があり、価格にもばらつきがあります。選ぶ基準や適正価格がわからず、導入しようかお悩みの方は多いかもしれません。この記事では、家庭用蓄電池の価格相場や価格にばらつきがある理由、選ぶときのチェックポイントなどを解説しています。蓄電池選びで後悔しないために、ぜひ役立ててください。
目次
1. 家庭用蓄電池の価格相場
家庭用蓄電池の1kWhあたりの価格は15万~20万円ほどです。蓄電容量はおおむね4.0~16.6kWhで、容量が大きくなるほど割安になります。設置工事費の目安は20万〜35万円ほどで、総額100万~250万円程度が目安となるでしょう。
ただし、蓄電池本体の仕様や寿命、販売店などによって価格は変動します。複数の候補の中から価格を比較する場合は「販売価格÷蓄電容量」で試算してみてください。
2. 価格が販売店によって異なる理由
同じ蓄電池の製品を扱っていても、販売店によって価格が異なる場合があります。なぜ価格差が出てしまうのか、理由は以下のとおりです。
2-1 仕様の違い
価格が異なる主な理由の一つとして、取り扱っている蓄電池の仕様の違いが挙げられます。
家庭用蓄電池は「特定負荷」と「全負荷」の2種類、さらに「単機能」と「ハイブリッド」の2タイプに分かれます。それぞれの特徴は以下のとおりです。
| 特定負荷 | 全負荷 |
|---|---|
| 特定の回路に電力供給 | 家中のほぼすべての回路に電力供給 |
| 単機能 | ハイブリッド |
|---|---|
| 蓄電池専用の パワーコンディショナーを使用する。 太陽光発電設備と蓄電池それぞれに 1台ずつパワーコンディショナーが必要となる |
太陽光用と蓄電池用が一体の パワーコンディショナーを使用する。 太陽光発電と蓄電池を組み合わせた一体型。 電力ロスが少ない |
特定負荷+単機能の蓄電池は価格面ではお得ですが、特定の回路のみの電力供給となります。夜間や停電時にも通常と変わりなく電気を使用したい場合は、割高にはなりますが、全負荷+ハイブリッドを選ぶと良いでしょう。
ただし、すでに太陽光発電のパワーコンディショナーが導入されているところに、最低限の費用で蓄電池を追加するなら、単機能を選んだ方がいいかもしれません。どのタイプがベストかは、施工会社としっかり検討しましょう。
2-2 仕入れ価格の違い
仕入れ価格が高ければ販売価格は高くなり、逆に仕入れ値を抑えることで販売価格も安くすることが可能です。
蓄電池の販売実績が豊富な販売店は大量仕入れによって単価が下げられるため、販売価格も安くなる傾向にあります。販売実績を確認するには、販売店のホームページの施工実績や口コミなどを見ると良いでしょう。
2-3 工事品質の違い
購入する方にとってわかりづらいのが工事品質です。前述のとおり、工事に使用する部材や職人レベルなどによっても変わりますが、標準的な設置工事費の目安は20万〜35万円ほどです。工事費が安すぎる場合は、工事保険に加入していなかったり人件費を削ったりして価格を下げている可能性があり、工事品質に影響する恐れがあります。
費用を抑えることは大切ですが、相場との乖離が著しい場合には注意が必要です。
2-4 保証・サポート内容の違い
家庭用蓄電池を導入した後の保証やサポートが充実しているかどうかも価格に影響するポイントです。保証・サポート内容が充実しているほど高額になりやすいですが、蓄電池は屋外に設置するため、天候などの影響により不具合が起きることもめずらしくありません。
設置するにあたって、メーカー保証や工事保証、自然災害補償、アフターメンテナンスなどがどのようになっているのか、事前にしっかり確認しておきましょう。
2-5 利益率の違い
販売店によってどの程度の利益率を設定するかは異なりますが、蓄電池の本体価格に上乗せされた利益率も販売価格に影響します。一般的に小売業の利益率は25~30%前後とされており、企業規模やエリアなどによって設定する利益率が変わるのが特徴です。
販売方法は訪問販売やハウスメーカー・工務店からの紹介、家電量販店、ネット販売とさまざまですが、特に訪問販売の利益率は高く、購入費用が高額になりやすい傾向にあります。販売方法による利益率の違いにも注意しましょう。
3. 家庭用蓄電池の正しい選び方
家庭用蓄電池は価格だけで選ぶのではなく、実際の暮らしをイメージして使いやすいものを選ぶことが大切です。ここでは、家庭用蓄電池の正しい選び方について解説します。
3-1 寿命
蓄電池の寿命は「サイクル数」または「使用期間」で判断します。
サイクル数は充放電可能な回数の目安を表す数値で、電池残量0%からフル充電し、再び残量0%まで使い切った状態が1サイクルです。
使用期間は、設置後に使い続けられる期間の目安で、家庭用蓄電池の場合は10~15年程度が一般的な目安とされています。
蓄電池の寿命はメーカーや機種で異なり、設置環境や使用状況などによっても変化します。交換にはまとまった費用がかかるので、できるだけ寿命の長い製品を選ぶと良いでしょう。サイクル数や使用期間を超えても使用できないことはありませんが、充電効率が落ち、最大容量も減少して使い勝手が悪くなります。
製品の寿命を意識して、交換にかかる費用を積み立てておくことをおすすめします。
3-2 容量
家庭用蓄電池の蓄電容量は、家族人数や使用状況を考慮して適切な容量を選ぶようにしてください。容量とは蓄電池に貯められる電力量(単位:kWh)のことを指します。
家庭用蓄電池として主流なのは、4.0~10kWhほどです。例えば4人家族の場合、7.0kWhの蓄電池があれば生活に最低限必要な電力の2~3日分を確保できると考えられます。
ただし、使用状況によってはさらに大容量の蓄電池が必要かもしれません。停電時の備えとしては容量が大きいほど安心ですが、導入時にかかる費用は高額になります。どのくらいの容量が必要かを「使用する電化製品の総電力(kW)×使用時間」で計算し、やや余裕のある容量の蓄電池を選ぶと良いでしょう。
3-3 保証内容
家庭用蓄電池を選ぶ際はメーカー保証の内容も必ず確認しましょう。特に次の3つは要チェックです。
- 無償の保証期間
- 容量保証
- 監視サービス
ほとんどのメーカーでは10~15年の保証期間を設けており、一般的な寿命といわれる15年まで保証を付けられますが、10年は無償、15年は有償とするパターンも少なくありません。11年目以降は蓄電池の寿命と重なるため、有償でも保証を延長するかどうかを検討する必要があるでしょう。
容量保証を設けているケースも多いです。蓄電池は長く使うほど蓄電できる電気が減ってしまいますが、10年または15年使用した後も、メーカーが定める容量以上を保証してくれます。さらに、蓄電池を24時間体制で遠隔監視するサービスを導入しているメーカーもあります。安心して長期間使用できるよう、これらの保証内容についてはしっかり確認するようにしましょう。
3-4 代表的なメーカーの蓄電池商品一覧
参考に、現在の代表的な蓄電池商品の情報をまとめました。
※「SII(環境共創イニシアチブ)」登録製品より、主要メーカーの商品を抜粋しています。
| 商品名 | メーカー | 蓄電容量 | 電力変換装置タイプ | 保証 |
|---|---|---|---|---|
| クラウド蓄電池システム | シャープ | 4.2~9.5kWh | ハイブリッド | 10年(有償で15年) |
| Enerezza | 京セラ株式会社 | 5.0~15.0kWh | 専用(単機能) | 15年 |
| トライブリッド 蓄電システム |
ニチコン株式会社 | 4.1~16.6kWh | 専用(単機能) ハイブリッド |
15年 |
| マルチ蓄電プラットフォーム | オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 |
6.5~16.4kWh | 専用(単機能) | 15年 |
| 太陽光発電用 ハイブリッド蓄電システム |
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 |
6.5kWh | ハイブリッド | 15年 |
| 創蓄連携システムS+ | パナソニック株式会社 | 6.3~12.6kWh | ハイブリッド | 10年(有償で15年) |
4. 家庭用蓄電池導入に活用できる補助金制度
蓄電池設置の費用を考えるときには、補助金が使えるかどうかも重要なポイントです。
国が実施している補助金制度を活用すれば、家庭用蓄電池の導入にかかる費用負担を軽減できます。2024年6月現在利用できる補助金制度は「DR補助金」で、最大60万円の補助が受けられます。詳細は以下の記事を参考にしてください。


また、独自の補助金制度を設けている自治体も多数あります。DR補助金とDER補助金はいずれか一つしか利用できませんが、自治体の補助金制度との併用は可能です。よりお得に家庭用蓄電池を導入するために、お住まいの自治体で活用できる補助金がないか、以下の検索サイトや役所に問い合わせて調べてみてください。
>一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会「地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」
5. 自家用車を利用する方はV2Hの選択肢も
太陽光発電と組み合わせて使用することで効果が高い家庭用蓄電池ですが、自家用車を所有するご家庭では、V2Hを導入するのも一つの方法です。V2Hとは、電気自動車やプラグインハイブリッド車の大容量バッテリーを家庭で活用する仕組みを指します。家庭用蓄電池よりも大量の電気を蓄えられ、太陽光発電システムとの併用で電気代の大幅な節約が期待できます。
ただし、車で外出している間は蓄電ができません。通勤などで日常的に車を利用するのなら、蓄電池もセットで導入しておくと安心です。
6. まとめ
家庭用蓄電池は、家族人数や使用状況に合う容量を選ぶことが大切です。また、補助金制度を利用するには、対象事業者として登録されている販売店が申請・施工する必要があります。
適切な蓄電池を勧めてくれる、実績豊富な販売店と出会うために、リフォームガイドを利用してみてはいかがでしょうか。リフォームガイドがご紹介するのは、厳しい審査をクリアした優良会社のみです。ご希望に合う会社への見積もり依頼から現地調査の日程まで調整しますので、手間もかかりません。ぜひお気軽にお問い合わせください。









 なら
なら

