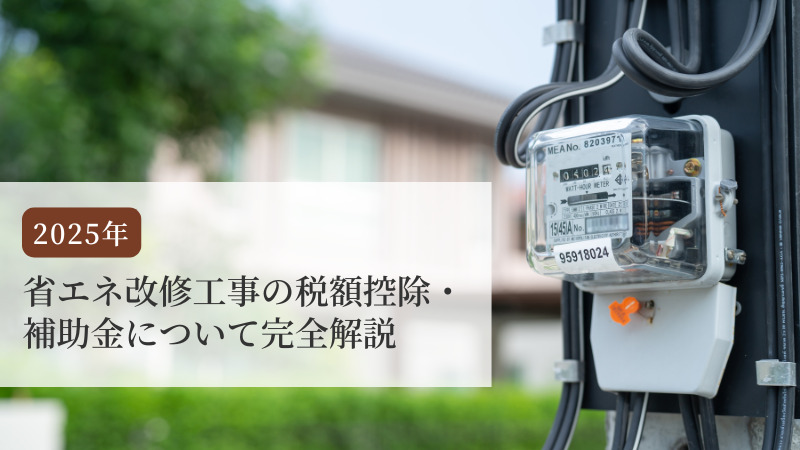
自宅のリフォームで、断熱工事やエネルギー効率の高い機器や太陽光発電設備の導入といった省エネ改修工事を行うと、税額控除や補助金制度などを利用でき、コストを抑えながらのリフォーム工事が可能になります。省エネリフォーム工事をお考えの方は、減税・補助金制度を申請するための条件についても、把握しておくと良いでしょう。
本記事では、省エネ改修工事で利用できる減税制度や各種補助金制度・優遇制度を紹介します。自宅のリフォームを検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
1.省エネ改修工事で使える減税制度とは?
自宅の改修で一定の省エネ改修工事を行う際には、減税を受けることができます。条件を満たす工事を行った後、確定申告で必要な手続きを踏むと、その年に納めた所得税・固定資産税から一定額が控除・減額され、還付金を受け取れるようになります。また、省エネ改修工事のために親・祖父母等から贈与された場合には一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。
2.省エネ改修工事で使える減税制度の減税額・適用条件
省エネ改修工事で使える減税制度について、実際の減税額や適用を受けるための条件、対象期間などを詳しく解説します。
2-1.所得税の控除
所得税の控除には、ローン利用の有無によって検討できる制度が変わります。
10年以上のローンを利用している場合のみ使える「住宅ローン減税」と、ローンを利用していなくても使える「リフォーム促進税制(投資型減税)」があります。ローンを利用している場合は、どちら適用するか選ぶことになります。
なお、所得税の控除は、納めている所得税額から控除されます。所得税の納税額が控除額より低い場合には、必ずしも最大控除額が控除されるわけではありません。
所得税控除の内容
| 控除期間 | 1年(改修工事を完了した日の属する年分) |
|---|---|
| 控除対象限度額 | 250万円または350万円(省エネ改修工事と合わせて太陽光発電設備の設置工事を行った場合) |
| 控除率 | 10% |
| 最大控除額 | 25万円または35万円(省エネ改修工事と合わせて太陽光発電設備の設置工事を行った場合) |
※対象工事の限度額超過分、およびその他リフォーム工事についても一定の範囲まで控除率5%で控除対象となる
| 控除期間 | 10年(改修後、居住開始した年から) |
|---|---|
| 控除対象限度額 | 2,000万円または3,000万円(長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合) |
| 控除率 | 0.7% |
| 最大控除額 | 140万円(2,000万円×控除率0.7%/年×10年間) |
所得税控除の適用要件
| 対象となる住宅の要件 |
|---|
|
| 改修工事の適用要件 |
|
| その他の適用要件 |
|
| 適用期間 |
| 2025(令和7)年12月31日までの竣工。 |
| 手続きの窓口 |
| 市区町村 |
| 必要書類 |
|
| 対象となる住宅の要件 |
|---|
|
| 対象となる改修工事の適用要件 |
|
所得税控除で必要な書類
減税制度の適用を受ける際には、確定申告の手続きが必要になります。確定申告用の書類など、所得税控除に必要となる書類は、以下の通りです。
| 必要な書類 | 内容 |
|---|---|
| 確定申告書 | 確定申告を行う際の申告書。税務署で取得。 |
| 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書 | 省エネリフォームによる減税制度を利用する場合に必要な書類。税務署で取得。 (耐震工事の場合は、住宅耐震改修特別控除額の計算明細書が必要) |
| (リフォーム工事完了後の)登記事項証明書 | 住宅の所有者、所在、広さ、構造などが記載された書類。法務局で取得。 |
| 増改築等工事証明書等 | 建築確認申請のない小規模なリフォームで、実際に工事を実施したと証明する書類。建築士から取得。 |
| 工事請負契約書 | 省エネリフォームとあわせて、その他の改修工事を行う場合に必要。リフォームの施工会社から取得。 |
| 住宅ローン残高証明書 | 現在の住宅ローン残高を証明する書類。リフォームで住宅ローンを利用する場合に必要。借入を行っている金融機関から取得。 |
| 補助金等の額を明らかにする書類(補助金等の交付を受ける場合) | 補助金を交付している機関から取得。 |
| 住宅耐震改修証明書(耐震リフォームの場合) | 耐震改修工事の実施を証明する書類。 各地方自治体から取得。 |
| 介護保険の被保険者証の写し(バリアフリーリフォームの場合) | 介護保険制度の利用に必要な保険証。 対象者が要介護認定または要支援認定を受けている場合に必要。 |
| 源泉徴収票(給与所得者の場合) | 2019年4月以降、添付は不要とされているが、申告書に内容を記載しなければならないため、勤務先企業から事前に発行してもらう必要がある。 |
確定申告は、リフォーム工事が完了して住宅に住み始めた年の翌年2月16日~3月15日の間に税務署またはe-taxによる電子申請で手続きを行います。たとえば、令和5年(2023年)に省エネ改修工事を実施した場合は、令和6年(2024年)2月からの確定申告での申告が必要です。
2-2.固定資産税の減額
省エネ改修工事を行った場合、確定申告による所得税の減税とは別に、省エネ改修工事の完了から3か月以内に市区町村などの地方自治体に所定の申告を実施すると、工事が完了した翌年分の「固定資産税」についても減額を受けられます。
| 減額の上限 |
|---|
| 固定資産税額の3分の1(家屋面積120㎡相当まで) |
| 減税期間 |
| 翌年度(1年度分) |
| 対象となる住宅の要件 |
|
| 改修工事の適用要件 |
|
| その他の適用要件 |
|
| 適用期間 |
| 省エネ改修工事の完了期間が平成20年(2008年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間。 |
| 手続きの窓口 |
| 市区町村 |
| 必要書類 |
|
2-3.贈与税の非課税措置
満18歳以上の個人が親や祖父母などの直系尊属から住宅取得等の資金を贈与された場合、一定金額まで贈与税が非課税となります。省エネ改修工事も「住宅取得等の資金」に含まれます。
非課税措置の内容
| 対象期間 | 2026年(令和8年)12月31日まで |
|---|---|
| 非課税枠 | 500万円または1,000万円(省エネ住宅・高耐震性住宅・バリアフリー住宅の場合) |
| 申告期間 | 贈与を受けた年の翌年3月15日まで |
非課税措置の適用要件
| 対象となる住宅の要件 |
|---|
|
| 対象となる改修工事の適用要件 |
次の1~8のいずれに該当する改修工事で、建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人により証明(「増改築等工事証明書」)がされたものであること。また、工事費の合計が100万円以上であること。
|
3.その他、省エネ住宅の改修工事で使える補助金一覧
省エネ改修工事では減税だけでなく、条件を満たすと使える補助金制度・優遇制度もあります。補助金制度を活用すれば、リフォーム工事の費用負担を一段と軽減できるでしょう。
ここからは、所得税減税制度以外に省エネ住宅の改修工事で使える補助金を紹介します。
3-1.省エネ改修工事で利用できる補助金一覧
省エネ改修工事では、国や地方自治体が、さまざまな補助金や助成金、給付金などを受け取れる制度を設けています。補助金制度を活用すれば、リフォームによる費用負担をさらに軽減可能です。
ここからは、2025年度最新の省エネ改修リフォーム工事で利用できる補助金について解説します
| <子育てグリーン住宅支援事業>※2026年度も事業継続 | |
|---|---|
| 補助金額 | 上限40万~60万円/戸 |
| 対象条件 |
<公募期間> |
| <先進的窓リノベ2025事業>※2026年度も事業継続 | |
| 補助金額 | 5万~200万円/戸 |
| 対象条件 |
<公募期間> |
| <給湯省エネ2025事業>※2026年度も事業継続 | |
| 補助金額 |
※補助上限: |
| 対象条件 |
<公募期間> |
| <既存住宅における断熱リフォーム支援事業> | |
| 補助金額 | 戸建て住宅:120万円/戸(玄関ドア5万円含む)
集合住宅(個別/全体):15万円/戸(玄関ドアも改修する場合は、上限20万円/戸)
※金額は上限額 |
| 対象条件 |
以下のいずれかを満たす工事。
<公募期間> |
| <長期優良住宅化リフォーム推進事業> | |
| 補助金額 |
※()内は三世代同居対応改修工事など所定のリフォームを実施した場合 |
| 対象条件 |
<公募期間> |
リフォームで使える補助金に関して、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
-300x109.jpg)
-300x109.jpg)
3-2.省エネ改修工事で利用できる優遇制度一覧
省エネ改修工事には、住宅金融支援機構と全国の金融機関が提携している全期間固定金利型住宅ローン「フラット35」の金利優遇を受けられる制度があります。
省エネ改修工事で利用できる優遇制度の詳細をみていきましょう。
| 優遇制度 | フラット35Sの金利優遇制度(住宅金融支援機構) |
|---|---|
| 補助金額 |
|
| 対象条件 |
|
4.省エネ改修工事の補助金等で迷った際の相談先
リフォームの際に便利な補助金ですが、さまざまな制度があるうえに、補助金額や適用条件も異なっており、初めて利用すると戸惑う方も多いかもしれません。補助金に関して分からない点があれば、専門機関や行政、リフォーム業者などに聞いてみるのが一番です。ここからは、省エネ改修工事の補助金等で迷った際の相談先を紹介します。
- (一般社団法人)住宅リフォーム推進協議会
住宅リフォームの推進に向け、ユーザーとリフォーム業者双方にとって有益かつ健全なリフォーム市場の形成を目的とする団体です。消費者からのリフォームに関する相談に答える専門ダイヤルである「すまいるダイヤル」を開設しているほか、全国に相談窓口を設けています。 - 市役所の担当課
住宅リフォームに関する相談ニーズの増加に伴い、全国の市町村でもリフォーム相談の担当課を設けるところが増えています。自分の住む地域でも利用できる窓口がないか調べてみてください。 - 補助金事業に「登録している」リフォーム業者
リフォームの補助金に関する相談では、補助金事業に登録しているリフォーム事業者に相談するのも1つの方法です。補助金事業に参加している業者なら、交付を受けるための条件や申請手続きの方法などについても知識やノウハウをもっています。補助金を活用したリフォームを行いたい場合は、一度相談してみると良いでしょう。
また、省エネ改修工事で補助金を利用する際は、業者選びが非常に重要です。補助金には、子育てグリーン住宅支援事業や長期優良住宅化リフォーム推進事業のように、登録事業者が行った工事しか交付の対象にならない制度があります。そのため、施工したのが登録業者でなければ、要件に適合した住宅であっても、補助金申請ができなくなってしまうのです。
省エネ改修工事を行う際は、必ず、リフォーム業者が利用したい補助金制度に登録しているか確認するようにしてください。
5.まとめ
自宅で省エネ改修工事リフォームを行う際、所得税や固定資産税の省エネリフォーム減税、各種補助金・優遇制度などを活用すれば、費用負担を抑えながら改修工事ができるようになります。
ただし、省エネ改修工事で補助金制度を利用する場合は、業者選びが重要です。
多くの補助金制度では、事前に登録を済ませているリフォーム事業者以外では補助金の申請自体ができません。リフォーム業者を決める際は、登録事業者かどうかもきちんとチェックする必要があります。
省エネ改修工事リフォームを考えているけれど、どの業者に任せればいいのかわからない、とお悩みの方には、複数の業者を同時に検索できるリフォームポータルサイトの利用がおすすめです。
リフォームガイドでは、ご希望のリフォーム内容に合ったリフォーム業者選びを経験豊富な専門スタッフがサポート。複数社の相見積もりが可能で、さらに補助金事業者のご紹介も可能です。登録は無料で行え、住宅のエリアやリフォーム箇所などを入力するだけで申し込みも簡単に行えます。
自宅の省エネ改修工事リフォームで減税・補助金制度の活用を検討中の方は、ぜひ一度、リフォームガイドの無料相談をご利用ください。









 なら
なら

