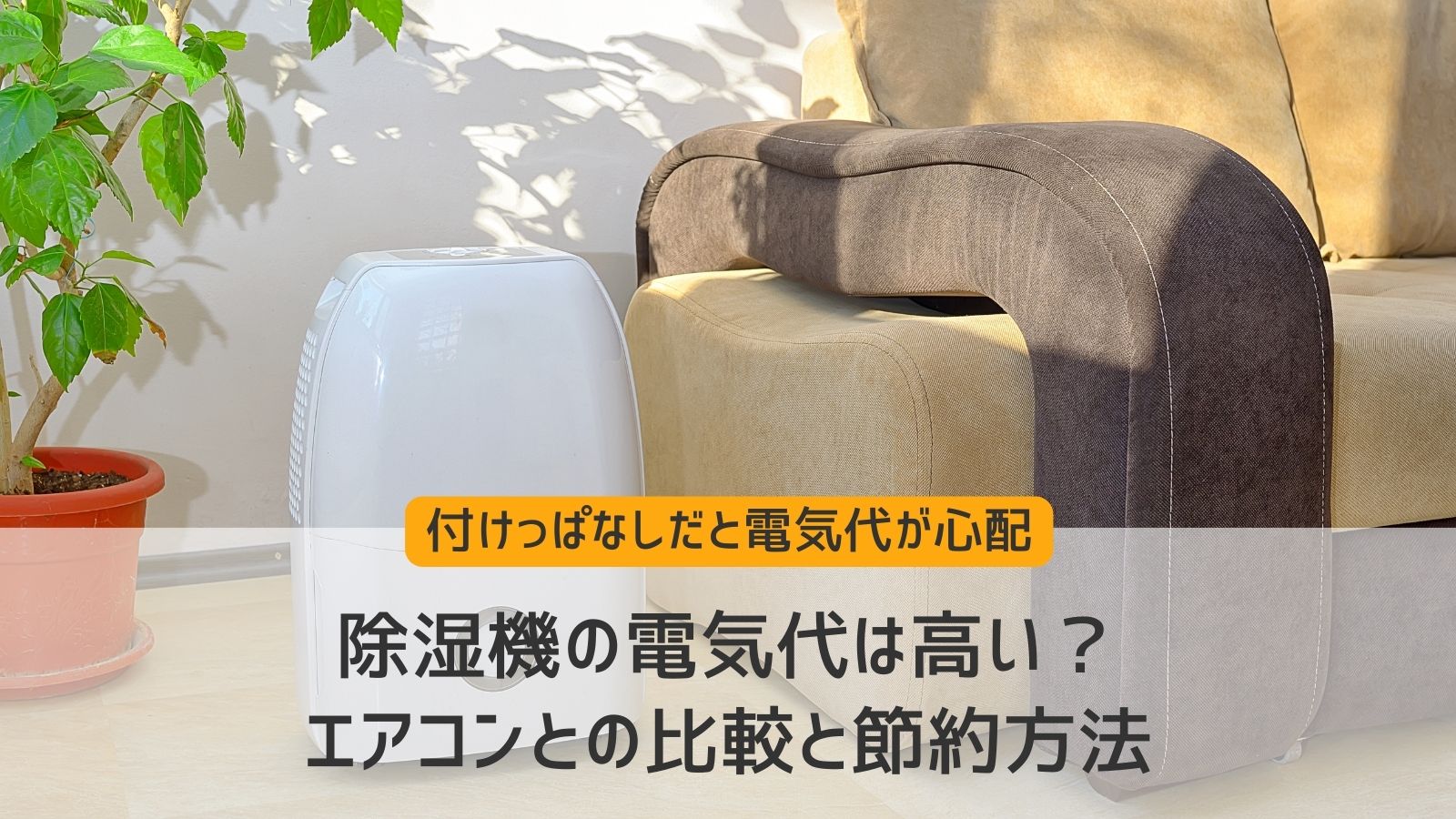
室内干しが多くなる梅雨や雪の時期には、部屋の湿度を下げてくれる除湿機が大いに役立ちます。
一方で、湿度の高い季節は使用頻度が高く一日中つけっぱなしにすることも少なくなく、電気代が高額にならないか心配という声も多く聞かれます。
本記事では除湿機を使用するとどれくらいの電気代がかかるのかを、エアコンだけを使う場合と比較して解説します。電気代の節約方法や、湿度に強い家づくりのポイントも紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
1.除湿機の電気代の計算方法
除湿機を含む電気製品の1ヶ月の電気代は、下記の計算式で算出します。
消費電力(W)÷1,000×使用時間(h)×使用日数×1kWhあたりの電気料単価※(円)
※電気料金の単価について
地域によって多少のばらつきはありますが、全国家庭電気製品公正取引協議会で目安としている31円/kWh(税込)で計算します(2023年12月時点)。
計算例:1ヶ月間、毎日8時間除湿機を使用した場合の電気代
除湿機には大きく分けて3つの種類があり、タイプごとに消費電力も200W~700W程度と開きがあります。
消費電力400Wの除湿機の場合、1ヶ月間の電気料金は下記のとおりです。
400W÷1,000×24時間×30日×31円=2,976円
2.【タイプ別】除湿機の電気代
ここではより具体的に、除湿機の種類ごとの電気代の違いと性能の特徴を見ていきましょう。
| 種類 | 消費電力の目安 | 1時間あたりの電気代 | 1ヶ月(30日)あたり の電気代* |
|---|---|---|---|
| コンプレッサー方式 | 125~400W | 3.9~12.4円 | 936~2,976円 |
| デシカント方式 | 285~480W | 8.8~14.9円 | 2,112~3,576円 |
| ハイブリッド方式 | 275~300W | 8.5~9.3円 | 2,040~2,232円 |
*1日8時間使用の場合
2-1.コンプレッサー方式
コンプレッサー方式の除湿機の電気代は、1時間あたり3.9~12.4円です。
コンプレッサー方式は、本体内部に取り込んだ空気を冷やし、結露を発生させることで除湿するタイプの除湿機です。熱が発生しないため、蒸し暑い夏場に使用しても室温が上がらず快適に過ごせます。
3つのタイプの除湿機の中で、最も消費電力が少ないというのも特徴のひとつ。在宅時間が長く使用頻度が高い方でも、電気代を抑えながら除湿機を使用できる点はメリットです。
デメリットとしては運転音の大きさが挙げられます。メーカー各社も静かに作動する除湿機の開発を進めていますが、それでも就寝時など静かな場所や時間帯での使用にはあまり向いていません。また、室温が低いと結露を作るのに時間がかかります。室内に干した洗濯物を早く乾かすことを目的に使用するにはやや力不足です。
2-2.デシカント方式
デシカント方式の除湿機の場合、1時間あたりの電気代は8.8~14.9円です。
デシカント方式は、本体内部にあるゼオライトという乾燥剤に、水分を吸わせることで除湿するタイプの除湿機です。水分を含んだゼオライトを内部のヒーターで乾燥させ、乾燥した空気を排出するという仕組みです。取り除いた水分は熱交換器で水滴に変え、タンクに貯められます。
空気をあたためて除湿することから、室温の低い冬でも除湿機能が下がりにくい傾向にあります。また作動音も静かな製品が多いのも特徴です。
ただし、ヒーターを使用するぶん消費電力が多く、電気代が高くなる傾向にあります。またあたたまった空気が排出されることで室温も上がるため、夏の暑い時期の使用には向いていないと言えます。
2-3.ハイブリッド方式
ハイブリッド方式の除湿機は、1時間あたりの電気代は8.5~9.3円ほどです。
コンプレッサー方式は夏、デシカント方式は冬の使用に適していると解説しましたが、ハイブリッド方式は2つの良いところを組み合わせたタイプの除湿機です。
室温や湿度に応じて運転比率を自動的に調整してくれるので、どの時期に使用してもしっかり除湿してくれる点が大きな魅力と言えます。
難点を挙げるとすると、いいとこどりをしているぶん本体価格が高い点です。また、メーカーにもよりますが、電気代も上記の2種類と比較して高くなる傾向にあります。
しかし、季節に左右されず一年中使用できるということを加味すると、使用頻度によってはコストパフォーマンスの良い買い物とも言えます。
3.除湿機とエアコン、電気代が安いのは?

最近のエアコンには除湿機能がついているものも多くあります。そのため、除湿機を使用せずエアコンの除湿機能を使用しようと考える方も多いでしょう。しかし気になるのは、除湿機とエアコンではどちらが電気代を安く抑えられるのか、ということです。
結論から言えば、除湿機よりエアコンの電気代の方が高くなります。
一般的なルームエアコンでの除湿機能の消費電力は約600Wですが、1時間あたりの電気代を計算すると18.6円です。
つまり、3種類ある除湿機のいずれのタイプと比較しても、エアコンの除湿機能のほうが1時間あたりの電気代が高いという計算になります。
ただし、エアコンの除湿能力は、除湿機単体と比較して高い傾向にあります。そのため短時間で除湿したいときや、湿度が著しく高い日には、エアコンを使用したほうが早く除湿できるということです。
[参考]エアコンの除湿機能
「弱冷房除湿」と「再熱除湿」の2つの種類があります。
「弱冷房除湿」というのは、取り込んだ空気を熱交換器で冷やして結露を発生させ、空気中の水分を取り出すタイプです。同じ方法で除湿し、室内に空気を戻す前にあたため直すステップが加わるのが「再熱除湿」です。一般的なエアコンには、再熱除湿方式が採用されています。
4.除湿機の電気代、節約方法
夏の蒸し暑い時期や室内干しをしている日は、特に除湿機の運転時間が長くなるため、どうにか電気代を抑えられないかと考えている方も多いでしょう。
除湿機の電気代を抑えるには、除湿機自体の使い方以外にも意識できるポイントがたくさんあります。ここでは特に知っておきたい6つのポイントをご紹介します。
4-1.運転モードに気を付ける

除湿機の性能が年々向上していますが、意識せずに消費電力の高いモードで運転してしまっている場合もあるため注意しましょう。
例えば、除湿能力の高い「速乾」機能は、短時間で部屋全体を除湿できるぶん消費電力も多くなります。特に湿度が高いときや早く除湿したいときには便利ですが、電気代を節約したい場合、長時間の使用はおすすめできません。
消費電力の多いモードの使用は必要最低限にし、普段は省エネモードで運転することで電気代を抑えることが可能になります。
4-2.室内干しするときは洗濯物の干し方を工夫する
室内に干した洗濯物を早く乾かすために、除湿機を使用している方も多いでしょう。しかしたくさんの洗濯物を密着させた状態で干してしまうと、空気の流れが悪くなり、洗濯物が乾くまでに時間がかかってしまいます。
そのため、除湿機の電気代を抑えながら洗濯物を乾かすためには、洗濯物の間に空気の通り道を作る工夫をするといいでしょう。
例えば、洗濯物同士の感覚が狭くならないように、こぶし1個ぶん程度の間隔を空けるのがおすすめ。空間にゆとりがあることで洗濯物から湿気が放出されやすくなり、除湿機能を最大限に生かせます。
4-3.サーキュレーターや扇風機と併用する
サーキュレーターや扇風機など、室内の空気を循環させてくれるアイテムを併用することでも、除湿機の効きをよくすることが可能です。
除湿機は本体周辺の空気しか取り込めないため、室内の空気が循環していない状態では、部屋全体の除湿が完了するまでに時間がかかります。サーキュレーターや扇風機で室内の空気を対流させることで、除湿機が湿気を含んだ空気を取り込みやすくなり、結果として短時間で除湿が完了するのです。
サーキュレーターや扇風機を使用する方法は部屋干しの際にも有効なため、洗濯物が乾きにくい時期にはぜひ取り入れてみましょう。
4-4.除湿機の手入れをこまめに行う
除湿機の性能を最大限に活用するためには、日ごろからこまめにお手入れしておくことも重要です。
除湿機の空気を取り込む部分にはフィルターが取り付けられており、ホコリが溜まると目詰まりを起こしてしまいます。目詰まりが起こると空気を取り込みにくくなり、除湿能力も落ちる原因にもなり得ます。
除湿能力の落ちた除湿機では、同じ量の空気を除湿するにも時間がかかり、余計な電力を消費してしまいます。最低でも2週間に1回は手入れするように意識しましょう。
4-5.除湿機を買い替える
今使っている除湿機が古い製品であれば、新しい除湿機に買い替えることで電気代を抑えられる可能性があります。
除湿機に限らず、家電製品の省エネ性能は年々向上しており、10年前のものと比較しても消費電力に大きな差があります。お持ちの除湿機がまだ現役であっても、場合によっては買い替えた方がトータルのコストが下がるケースもあるのです。
また、コンプレッサー方式・デシカント方式の除湿機をハイブリッド方式の製品に買い替えるのもおすすめ。室温や湿度に合わせて運転してくれるため、電気代を抑えることが可能です。
4-6.除湿に効くリフォームをする
「湿度に強い住宅」にリフォームすることで除湿機の運転時間を短くできるため、結果的に除湿機の電気代の節約にもつながります。

例えば、湿気がこもりやすく、カビの繁殖に悩む方が多いクローゼットは、調湿建材を使用したリフォームを実施するのがおすすめ。調湿建材は室内の湿度を調整する機能があるため、わざわざ除湿剤や除湿機を使わなくても、クローゼット内の湿度を適当に保ってくれます。
湿気が溜まりやすい部屋があることに悩んでいる場合は、ルームドライヤーが便利です。ルームドライヤーを取り付けると、壁に空けた穴から、ホースを通じて湿気を含んだ空気が屋外に排出されます。除湿機で面倒に感じやすい、水の処理の手間がかからない点が魅力です。
室内干しをする頻度が高い家庭であれば、浴室暖房乾燥機を設置するリフォームもおすすめです。住宅の中で最も湿度の高い浴室に乾燥機能を取り入れることで、浴室内のカビを防止するだけでなく、雨や台風の時期の物干し場としても利用できます。
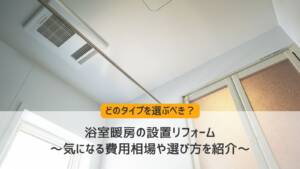
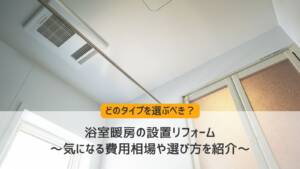
除湿に効くリフォームにはさまざまな種類があるため、リフォーム会社に相談し、予算やライフスタイルに合った施工を選ぶようにしましょう。
5.まとめ
除湿器の電気代を節約するためには、ライフスタイルに合った機種を選んだり運転モードに気を使ったりすることも重要ですが、住宅自体の湿度に対する耐性を高めることも大切です。
湿気に強い住宅にするためのリフォームにはさまざまな種類があるため、リフォーム会社と相談しながら決めるといいでしょう。
リフォームガイドでは、湿気対策に有効な施工に強いリフォーム会社を多数ご紹介しています。ぜひお気軽にご相談いただき、ジメジメしない快適な住まいを手に入れてください。








 なら
なら

