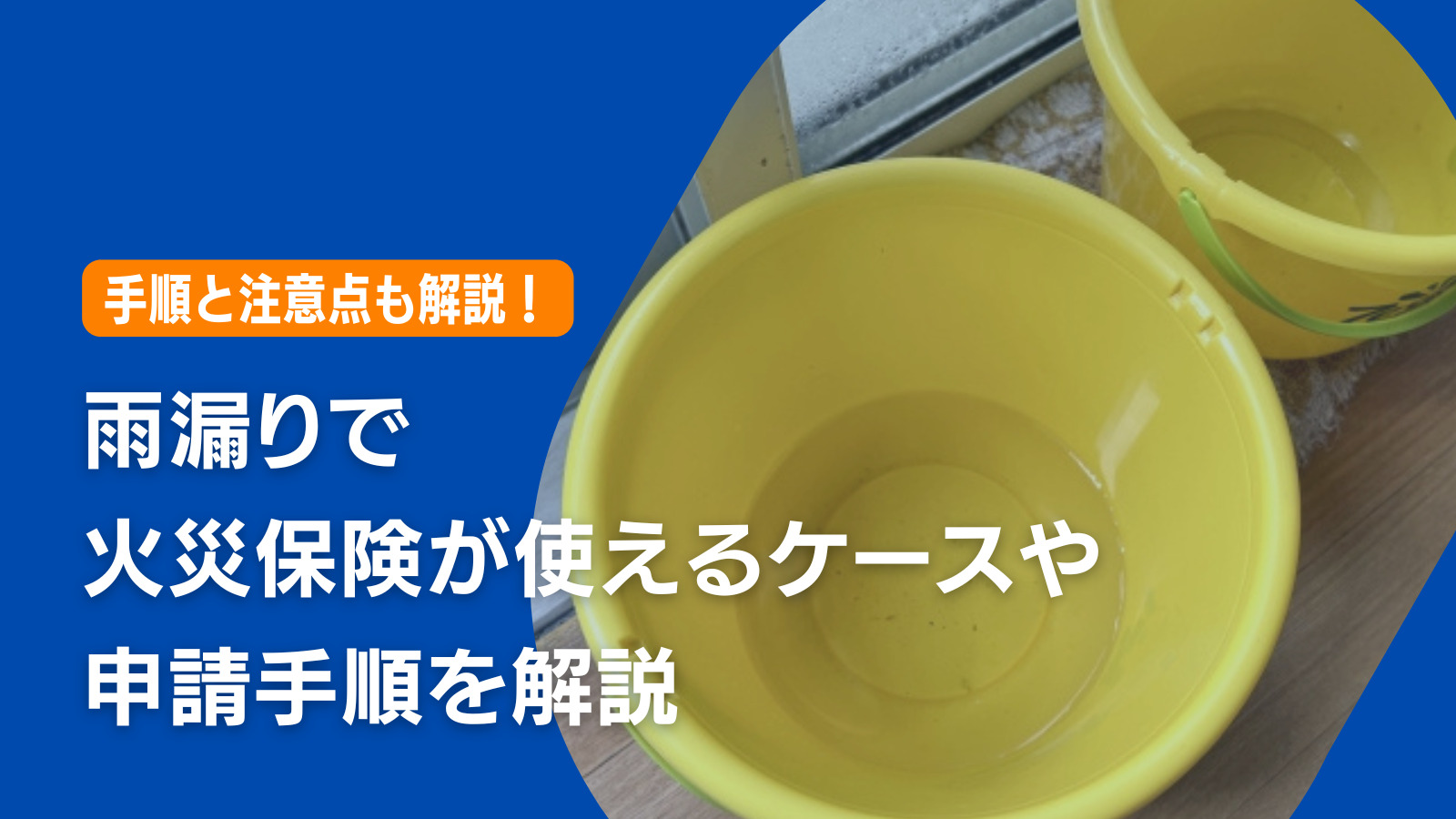
雨漏りで家の中が水浸しになったり、台風や豪雨のあとに雨漏りをみつけて、火災保険は使えるのかどうか疑問に思ってはいませんか?
今回は、雨漏り修理で火災保険が適用になる可能性が高いケースと、難しいケースについて解説していきます。
また、雨漏りで火災保険を使う際のポイントや、保険会社へ申請して工事するまでの流れや、施工業者を選ぶ際の注意点も紹介します。
目次
1.雨漏りで火災保険は適応される?
雨漏りで火災保険が適応されるケースがありますが、どんな雨漏りでも火災保険が下りるわけではありません。「自然災害による雨漏り」の場合に限り、火災保険が適用されます。
火災保険で適用される自然災害は、以下のとおりです(ご加入の火災保険によって表現は異なる場合があります)。
火災保険で適用される自然災害
- 火災
- 落雷
- 風災
- ひょう災
- 雪災
- 水災
これらの自然災害によって、屋根や外壁などが破損してしまい、雨漏りが発生した場合には保険金が支払われます。
2.火災保険が適用できる可能性がある雨漏りのケース
火災保険が適用になる可能性の高い、自然災害による雨漏りのケースを解説します。
また、雨漏りでなくても、自然災害による破損であれば火災保険の適用対象となる可能性があります。雨漏り箇所以外にも破損箇所がないか、合わせて確認しましょう。
2-1.台風によって屋根が破損
台風で屋根の棟板金が飛んでしまったり、瓦が落下した結果、雨漏りが発生した場合です。台風による屋根の破損は、よくある被害の1つです。
【よくある破損状態】
棟板金(屋根の頂上部分等の金属部分)の剥がれ、瓦の滑落、瓦のずれ
※棟板金補修作業の様子

2-2.強風によって外壁が破損
強風によって飛来物が外壁に当たり、破損してしまった場合です。
【よくある破損状態】
(飛来物による)外壁の穴あき、瓦の破損
2-3.ひょうが降って屋根が破損
大きなひょうが降った結果、屋根が破損してしまい、雨漏りが発生した場合も火災保険が適用される可能性が高いです。
【よくある破損状態】
(ひょうによる)金属屋根などの穴あき
2-4.雪の重みで屋根が破損
積雪による重みで、屋根や雨樋などが破損した場合です。カーポートなども破損した場合は、保険が適用される可能性があります。
【よくある破損状態】
瓦のずれ、屋根材のゆがみ、雨どいのゆがみ
3.火災保険の適応が難しいケース
火災保険が適用になるのは、風災など、自然災害による雨漏りや屋根の破損です。
そのため同じ雨漏りでも、原因によっては火災保険の適用が難しいケースがあります。ここでは、火災保険が使えない代表的な例を紹介します。
3-1.経年劣化
雨漏りの原因が建物の経年劣化である場合、火災保険は適用になりません。経年劣化とは、時間の経過とともに屋根や構造が劣化し、ひび割れや亀裂が生じることです。
雨漏りは、経年劣化が起きている家を、さらに劣化させます。屋根の下地や柱、土台など、家を支えている構造部分にまで傷めてしまう恐れがあります。雨漏りが起きたらなるべく早く対応し、根本をなおす補修やリフォームをしましょう。
3-2.新築時・リフォームでの施工不良
新築時やリフォームした際の施工不良が雨漏りの原因の場合も、火災保険は適用になりません。自然災害ではなく、人為的なミスによるものであるためです。
もし新築してから10年以内の雨漏りであれば、「10年間の瑕疵担保責任補償」が適用になり、無償で修理してもらえる可能性があります。新築を建てたハウスメーカーや工務店に相談してみましょう。
また、リフォームしたことが雨漏りの原因だと考えられる場合は、リフォーム会社に相談して、修理してもらいましょう。ただし、保証期間が定められていることがあるため、なるべく早めに相談するのがおすすめです。
4.雨漏りで火災保険を使うときのポイント
雨漏り修繕で火災保険の申請を行う際には、3つの点に注意しましょう。
- 加入している火災保険のタイプを確認する
- 加入している火災保険の適用条件を確認する
- 被害を受けた日から3年以内である
加入している保険会社やプランによっても異なるため、事前に保険証券の確認や保険会社に問い合わせて確認しておくことをおすすめします。
4-1.加入している火災保険のタイプを確認する
加入している火災保険のタイプによって、受け取ることができる金額が異なります。保険証券を見て種類を確認し、目安となる金額を想定しておきましょう。
最近の保険契約のほとんどは「免責型」ですが、十数年前に加入した場合は、「フランチャイズ型」の可能性があります。
ここでは、免責型とフランチャイズ型についてそれぞれ紹介します。
免責型
免責型とは、加入時にあらかじめ「免責金額」を決めておくタイプです。免責金額とは、実際に損害を被った際に支払われる保険金から、差し引かれる金額のことです。
つまり「免責金額=自分負担額」となります。そのため、損害額(補修工事にかかった費用など)が免責金額を下回る場合、保険金は受け取れません。
※保険会社によって免責金額の設定は異なります。
- 保険金を受け取れるケース:損害額>免責金額
自然災害によって被った損害額が免責金額を上回る場合は、損害額から免責金額を差し引いた金額が保険金として支払われます。保険金=損害額-免責額
- 保険金を受け取れないケース:損害金<免責金額
自然災害によって被った損害額が免責金額を下回る場合は、保険金は支払われません。全額が自己負担となります。
フランチャイズ型
フランチャイズ型の場合、一般的には20万円以上の損害に対応する火災保険です。つまり、損害額が20万円未満の場合は保険金が支払われませんが、20万円以上の場合は全額補償されます。
免責型との違いは、損害額が20万円以上であれば自己負担が発生しない点です。現在は免責型が主流といえますが、かつてはフランチャイズ型が多かったようです。加入している保険がどちらのタイプなのかについては、保険証券を見て確認しておきましょう。
4-2.加入している火災保険の適用条件を確認する
火災保険の申請をする前には、加入している火災保険の適用条件を確認しておきましょう。加入している火災保険の補償内容に「風災」「ひょう災」「雪災」が含まれていれば、自然災害による雨漏りが適用になる可能性があります。
雨漏りは「水」をイメージするため、水災が含まれているかチェックする方が多いかもしれません。しかし火災保険で水災といえば、台風や暴風雨による洪水や土砂崩れの損害が対象です。
4-3.被害を受けた日から3年以内である
火災保険は被害が発生してから、原則として3年以内に保険金を請求する必要があります。自然災害に遭ったのにもかかわらず、気がつかずに放置してしまうと時効になり、保険金を請求できなくなるので注意しましょう。
なぜなら、自然災害から一定以上の期間が経過すると、自然災害に起因するものなのか、それとも経年による劣化なのか判断できなくなるからです。
自然災害が発生した場合は家の状態を確認し、被害が生じている場合はなるべく早く保険会社へ保険金を請求するようにしてください。
5.保険金が雨漏り修理に適用されるまでの手順
雨漏りの調査や見積もりを依頼し、雨漏り修理業者へ工事を依頼するまでの流れを、6つのステップで紹介します。
①修理業者に調査・見積もりを依頼
雨漏りを発見したら、まずはリフォーム会社または雨漏り修理業者に調査と見積もりを依頼し、雨漏りの原因を特定してもらいます。
このときに火災保険を使いたい旨を伝え、申請について相談できるか聞いておいてください。火災保険の申請について詳しい会社であれば、火災保険が使えるかどうかの判断をしてもらいやすく、また申請手続きを手伝ってくれるケースもあります。
自分では屋根部分の写真撮影は難しいことが多いので、被害状況が分かる写真撮影もお願いしておくとよいでしょう。
②火災保険会社に連絡
雨漏りの原因や被害状況、修理にかかる費用が分かったら、次に保険会社に連絡します。
保険証券や雨漏り修理の見積書、屋根の点検報告書などを手元に準備し、雨漏りが発生した日時や状況を説明できるようにしておくとスムーズに進められます。
保険会社からは、今後の手続きや申請に必要な書類について説明があります。
③保険会社からの書類を確認して申請
保険会社から関係書類が送られてきたら、該当する項目を記入し、必要書類とともに提出します。
保険会社によって多少内容が異なることもありますが、申請時に必要な書類は以下の通りです。
- 火災保険証券
- 保険金請求書
- 被害状況報告書
- 修理業者の見積書
- 被害状況が分かる写真
④損害鑑定人の現場調査
保険会社から委託を受けた損害鑑定人が、雨漏りした現場を調査します。損害鑑定人は現場を調査し、損害状況の確認や、自然災害による被害なのか判断します。
損害鑑定人が現場調査した結果を報告書としてまとめ、委託された保険会社へ提出します。
⑤保険金の支払いが決定
損害鑑定人の調査報告書により保険金の対象であると判断されたのちに、契約者に保険金が支払われます。
保険金の支払いが決定後、指定した金融機関の口座に振り込まれるのが一般的です。
⑥雨漏り修理業者へ依頼する
保険会社から保険金が支払われる旨の連絡がきたら、雨漏り修理業者へ工事を依頼してください。
担当者からもし「火災保険が使える」と説明されたとしても、実際に申請が下りてから工事を依頼するようにしましょう。
6.火災保険を使って雨漏りの修理業者を選ぶときの注意点
火災保険を使って雨漏りを修理できないかお考えの場合は、火災保険の申請を経験しているリフォーム業者に依頼することで、安心してスムーズに申請できます。
依頼する前に以下の点を確認してください。
- 保険申請のサポートができるか
- 地元の業者で、同じ地域で火災保険申請をしたことがあるか
保険申請のサポートに慣れている業者であれば、保険会社に提出するための書類や写真の準備といったサポートが受けられます。
また、同じ地域で火災保険申請をサポートしている業者の場合、同様の被害で保険金申請をしている可能性があります。
お近くで、火災保険申請のサポートもできる業者を探してみましょう。
保険金詐欺の業者に注意する
残念ながら火災保険を利用した詐欺を行っている業者もいます。
ここでは主な詐欺手法について3つ紹介します。事前に手法を知っておくことで、詐欺を未然に防ぐことにつながります。
・うその被害理由を申告するよう促される
自然災害による被害でないのに、保険金が支払われるよう虚偽の報告を促させることがあります。
自然災害による被害ではない場合には、その業者は利用しないようにしましょう。虚偽の被害申告は、顧客自身が詐欺に加担したとみなされる場合があります。
・保険金が支払われるからと、すぐに工事契約を結ばせる
「100万円の保険金が支払われるから、先に工事を進めましょう」などと提案し、急いで契約させることがあります。しかし、実際には保険金が支払われず、全額自己負担となるトラブルが実際に発生しています。悪質な場合は、故意にその場で破損させ、自然災害と偽ることもあります。
必ず保険金が支払われることが確定してから契約を進めてください。保険金は工事契約を結ぶ前に支払われるかどうかが決まりますので、焦らずに結果を待ちましょう。
・申請のための手数料が高い
申請代行手数料で、支払われた保険金の20〜40%を取るなど、報酬金額が高すぎる場合があります。優良業者であれば、手数料は無料か数万円程度が一般的です。
事前に手数料がかかるかどうかを確認しましょう。


リフォームガイドでは、火災保険を使ったリフォームの業者探しもサポートしています。利用は無料なので、以下の「一括見積もり依頼」フォームから気軽にご相談ください。
7.まとめ
雨漏り修理で火災保険が使える可能性が高いケースと難しいケース、保険会社へ申請して工事するまでの流れ、施工業者を選ぶ際の注意点について解説してきました。
火災保険が補償する損害は、自然災害による雨漏りであり、経年劣化による雨漏りは対象になりません。また火災保険の契約内容によっては、風災(自然災害)による雨漏りであっても対象にならない可能性があります。
記録的な豪雨や台風の後は、天井や軒裏に雨漏りがないか確認するようにしてください。雨漏りした形跡を見つけたら、信頼できるリフォーム会社や雨漏り修理業者へ調査を依頼するようにしましょう。




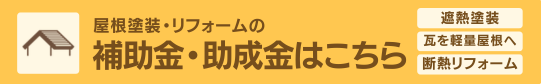




 なら
なら

