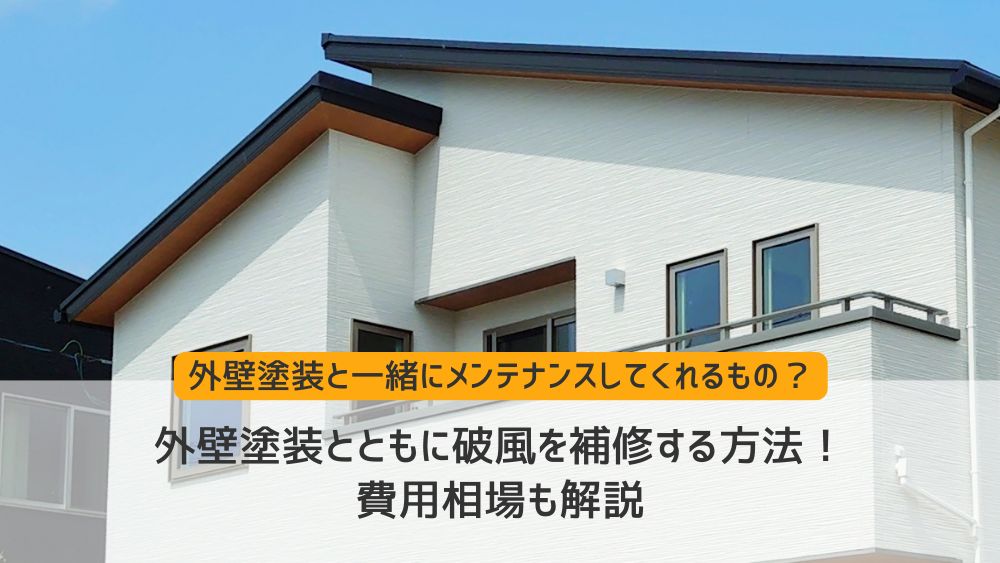
外壁や屋根のメンテナンスを考える際、破風板の劣化も見逃せない重要なポイントです。経年劣化によって破風板が腐食や変色すると、建物の美観を損なうだけではなく、雨漏りや害虫被害のリスクも高まります。
外壁塗装を行う際に、破風も必ずメンテナンスしてくれるとは限らないので、破風の傷みも気になる場合は見積もり時に必ず一言確認しましょう。
この記事では、外壁塗装と同時に行う破風のメンテナンス方法を紹介します。塗装から板金巻き、交換まで、状態に応じた適切な補修方法や費用相場、施工手順を見ていきましょう。安心して業者選びをするための判断材料として活用してください。
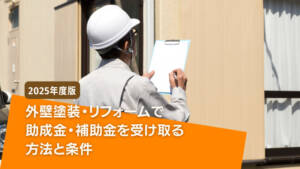
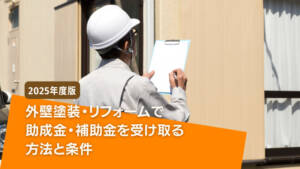
目次
1.破風とは?塗装は必要?
破風(はふ)は屋根端部の重要な構造部材で、風雨から建物を守る役割があります。外壁や屋根と同様に定期的な塗装メンテナンスが必要な部位です。
適切にメンテナンスすれば、建物の耐久性と資産価値を維持できます。
1-1.破風とは?鼻隠しとは?

破風は切妻屋根や片流れ屋根のケラバ(三角形状の側面)につく部材で、「風を破る」という字の通り、強風から屋根を保護する重要な役割を担っています。一方、鼻隠しは軒先の端部に取り付けられます。
両者は屋根端部という点で似ていますが、雨樋の有無が大きな違いです。破風には雨樋が付かず、鼻隠しには雨樋が取り付けられるのが特徴です。
いずれも建物の構造と美観を支える重要な部材で、適切なメンテナンスが必要となります。破風や鼻隠しの劣化は、単なる見た目の問題だけではなく、雨漏りや構造的な問題にもつながる可能性があるため、早めにみつけて対処しましょう。
1-2.破風は塗装のメンテナンスが必要
破風は常に風雨や紫外線にさらされており、定期的な塗装メンテナンスが必要です。塗装することで新しい塗膜ができるため、水分の浸入を防ぎ、腐食や変形を抑制できます。
破風の劣化が気になる頃には、外壁もメンテナンスの時期が近づいているケースも少なくありません。そのため、外壁塗装と同じタイミングで破風も塗装するのがおすすめです。
ただ、外壁塗装を依頼すると、必ず破風のメンテナンスも対応してくれるというわけではありませんので、破風についても処置してもらえるか、見積もり時に必ず確認しましょう。
塗装すると見た目も美しくなるため、建物全体の印象をアップさせる効果があります。反対に、塗装を怠ると、破風の劣化が進み、最悪の場合は雨漏りや構造的な問題につながるでしょう。
特に雨の多い地域や海岸部では塩害や湿気の影響により、劣化が進んでしまうなど、立地条件や使用材質によって適切なメンテナンスサイクルは異なります。
破風だけでなく、定期的な外壁・屋根の塗装は、建物を維持するためにも必要です。
1-3.破風に使われている材質
破風の材質は、耐久性とメンテナンス頻度に大きく影響します。ここでは、破風に使われている主な材質を紹介します。
| 材質 | 特徴・利用箇所 | 特長 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 金属系 | 木製の破風板に ガルバリウム鋼板などの 金物を被せた仕様が一般的 |
|
|
| 木製 | 築20年以上の住宅で よく見られる伝統的な仕様 |
|
|
| モルタル | モルタル外壁の住宅に 多く見られる仕様 近年の新築では減少傾向 |
|
|
| 窯業系 | 長期的に見ると コストパフォーマンスが高い |
|
|
2.外壁塗装をするときに可能な破風の修理
破風の劣化状態は軽度から重度までさまざまですが、適切な修理方法を選択すれば、効率的かつ経済的にメンテナンスできます。
また、外壁塗装と同時に行うことで足場代などの工事費用も抑えられます。
2-1.再塗装
再塗装は、破風板の塗膜劣化が軽度な場合に適した修理方法です。築10年程度までの比較的状態の良い破風板であれば、再塗装による対応が最も効率的です。新しい塗膜によって破風板をコーティングすることで、防水性もアップし、美観を保てます。
特に重要なのは塗装前の下地処理で、既存塗膜の状態を丁寧に確認し、必要に応じて剥離や清掃を行います。また、外壁塗装と同じ塗料を使用することで、建物全体の統一感も生まれるため、見た目をきれいにしたいときにもおすすめです。
2-2.板金巻き
板金巻きは、塗膜の剥離が進行している場合に有効な修理方法です。ガルバリウム鋼板で破風板を覆うことで、高い防水性と耐久性を確保できます。特に木製破風板の場合は防火性も向上するため、安全性の面でもメリットがあります。
施工には専門的な技術が必要ですが、一度施工すれば長い耐久性が期待でき、メンテナンス頻度も大幅に減少するでしょう。また、さまざまな色や仕上げの選択が可能で、外壁との調和も考慮した施工ができます。
費用は再塗装よりも高くなりますが、長期的な維持管理コストは抑えられます。特に海岸部や積雪地域など、厳しい気象条件にさらされる地域では、板金巻きによる保護が効果的です。
2-3.破風板の交換
破風板に腐食や構造的な損傷が見られる場合は、交換が必要です。新しい破風板には、耐久性と防火性に優れた窯業系ボードが使われます。交換工事では、下地の状態確認や防水処理も同時に行うため、建物の耐久性を大きく向上させられます。
交換後は、定期的に塗装をすることで、長持ちするようになります。工事費用は再塗装や板金巻きよりも高くなりますが、建物の安全性を保つためにはおすすめの施工方法です。
また、交換すると今の建築基準にあった施工方法や材料を選べるため、耐震性や防火性能の向上にもつながります。
3.外壁塗装と同時に破風を塗装するメリット
外壁塗装と同時に破風を塗装することには、さまざまなメリットがあります。
- 足場費用を節約できる
- 長期的な維持管理計画が立てやすくなる
- 外観の統一感を出せる
最も大きなメリットは費用面です。別々に工事すると余分なコストが発生しますが、足場設置費用を一度で済ませることができます。
また、塗装のメンテナンスサイクルを外壁と合わせることで、長期的な維持管理計画が立てやすくなります。外壁塗装の耐用年数は使用する塗料にもよりますが、一般的に10~20年程度です。破風も同時期に塗装すれば、次回の塗り替え時期を同じタイミングに設定できます。
さらに、外観の統一感も重要なメリットです。同じ塗料を使用することで、色味や光沢の違いによる違和感を避けられます。特に破風は建物の印象を大きく左右する部位であり、外壁との調和は美観維持の観点からも重要です。
4.外壁塗装で破風を塗る場合の費用相場
破風だけを塗る場合は一般的な住宅だと総額で15〜30万円ほどかかります。
破風を塗る場合にかかる費用の相場は1平方メートル当たり800〜1,500円です。下地処理や塗装費用が含まれていますが、足場や洗浄、養生の費用は含まれていません。
5.外壁塗装で破風を塗るなら何色がオススメ?
外壁塗装で破風を塗る場合に適した色は住宅によって変わります。一般的には、外壁または屋根と似た色を使うケースが少なくありません。
特に多いのは、茶色系や白系、クリーム系でしょう。


出典:https://freshhouse.co.jp/case/27583/
グリーンやホワイトといった明るい外壁に、クリーム色などホワイト系の破風をあわせています。
一方で、濃色の屋根・外壁には黒やブラウンの破風を合わせるとしっくり来ます。


出典:https://freshhouse.co.jp/case/20726/
ブラウンの外壁材に茶色の破風をあわせている事例です。こちらの住宅は、サッシの色も黒で落ち着きのあるカラーでまとめています。
色を選ぶのに迷ってしまう人は、屋根か外壁のうち、色が濃い方に合わせましょう。破風だけ別の色にしてしまうと、屋根と外壁のどちらとも合わずにちぐはぐな印象を与えてしまう恐れがあります。
また、破風を雨樋やサッシの色に合わせる方法もあります。破風の色を合わせることで、家全体の統一感が出せるため、おすすめの方法です。
6.外壁塗装とともに破風を塗装する手順
外壁塗装を悪徳業者に依頼してしまうと破風を塗らないケースがあります。破風を塗る手順を把握しておけば、悪徳業者が提出してきた見積もりで問題点を発見しやすくなるでしょう。
破風を塗る手順は以下の通りです。各項目が見積もりに入っているか、見積もり内容の説明時に工程に抜けがないかを確認しましょう。
- 足場の設設置
- 下地処理
- 養生
- 下塗り
- 中塗り・上塗り
6-1.足場の設置
外壁塗装で破風を塗る場合、足場を設置します。
破風は高所にあります。足場なしで行うと安全性と作業性が確保できないため、作業員の安全と塗装の質を確保するためにも、足場は欠かせません。
6-2.下地処理
足場を設置したあとは、下地処理をします。
破風の下地処理とは、破損箇所を補修したりサンドペーパーで研磨したりすることです。補修をせずに塗装すると、すぐにはがれてしまうので、大事な工程です。
劣化している箇所も、下地処理と同時に補修を行います。
6-3.養生
下地処理後は養生をします。養生とは、塗らない場所をテープやビニールシートで保護する作業です。
塗料の飛散を防ぐことはできないため、養生は必要です。
6-4.下塗り
養生をしたら「シーラー」と呼ばれる塗料で下塗りをします。破風の下塗りは、使われている素材によって使われる塗料が違います。
破風の素材には木材のほか、金属というケースもあります。それぞれの素材にあった下塗り塗料を塗っていきます。
6-5.中塗り・上塗り
下塗りが完了したら仕上げ塗装を2回行います。1回目を「中塗り」、2回目を「上塗り」と呼びます。
仕上がりのむらをなくし、ツヤを出すためにも、中塗りと上塗りを行います。
7.外壁と破風の塗装をする場合の注意点
破風を塗装する場合、3つの注意点があります。
- 他の部位と一緒に塗装する
- DIYは避ける
- 業者は相見積もりで選定する
具体的にどのように注意するかを解説していきます。
7-1.他の部位と一緒に塗装する
破風を塗り替えする場合、屋根や外壁なども一緒に塗装しましょう。破風だけを塗装すると足場や養生の費用が高くなるからです。
破風の塗装で1回、外壁の塗装で1回というように工事を分けてしまうと、そのたびに足場を設置しなければいけません。
足場の設置には5〜20万円程度の費用がかかるため、分けて塗装すると2回分の足場代が発生してしまいます。
破風と屋根、外壁をまとめて塗装すれば、個別で工事をするよりも費用が節約できるでしょう。
家の外増全体を塗装をすると、家の外観を一層して美しく保つことができます。可能なら、外壁や屋根も同時に塗装するよう検討してみてください。
7-2.DIYは避ける
破風は面積が限られているので、破風だけでもDIYで塗装しようと思う人もいるかもしれませんが、基本的にはおすすめしません。
破風の塗装は高所作業となり、作業中に落下すると大きな事故に繋がります。
また、破風以外の塗装はDIYでは難しいので、破風だけを塗装して他の部位を業者に依頼すると効率もよくありません。
さらに、DIYで塗ると色むらや塗り損ねが出る可能性があります。業者が塗った場所との仕上がりの差が目立つ恐れもあるでしょう。
たとえ破風の塗装だけであってもDIYは避けましょう。
7-3.業者は相見積もりで選定する
破風の塗装をする場合、外壁塗装の業者は相見積もりで探しましょう。相見積もりとは、2、3社に同じ工事条件で見積もりを出してもらうことです。
相見積もりで価格が他社よりかけ離れている業者には依頼しないようにしましょう。
他社よりも極端に安い業者も避けましょう。中塗りを省くなど、必要な工程を省略して仕上がりが悪くなったり長持ちしなかったりといった問題につながる恐れがあります。
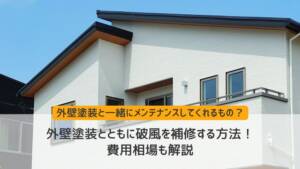
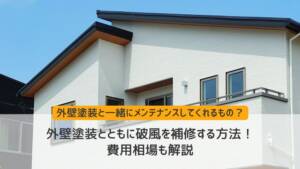
8.まとめ
破風は屋根の端部を保護する重要な部材で、建物の耐久性を維持するには破風の定期的なメンテナンスが不可欠です。劣化状態に応じて、再塗装、板金巻き、交換という3つの修理方法を検討します。
外壁塗装と同時に破風のメンテナンスを行うことで、足場代の削減や工期の短縮など、コスト面でのメリットが得られます。また、外壁と破風のメンテナンスサイクルを合わせれば、長期的な維持管理計画も立てやすくなるでしょう。
業者を選ぶには、複数社から見積もりをとり、破風の修理実績がある業者を選ぶことをおすすめします。定期的な点検をして、劣化が見られた場合には、早めに修理しましょう。
外壁や破風を修理しなければならないとなった場合、破損の原因によっては火災保険が適用できる場合があります。こちらの記事で確認してみましょう。
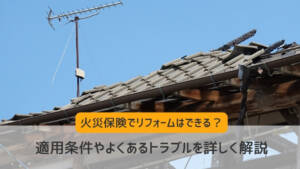
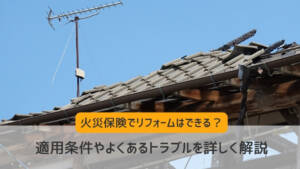




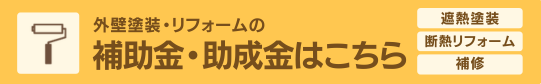



 なら
なら

