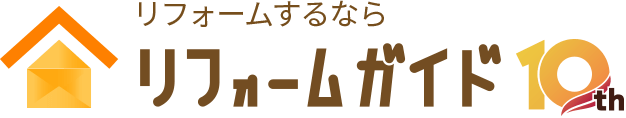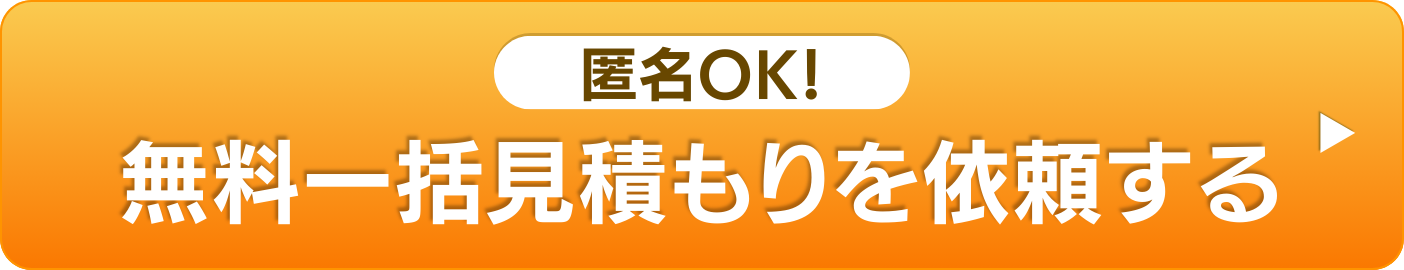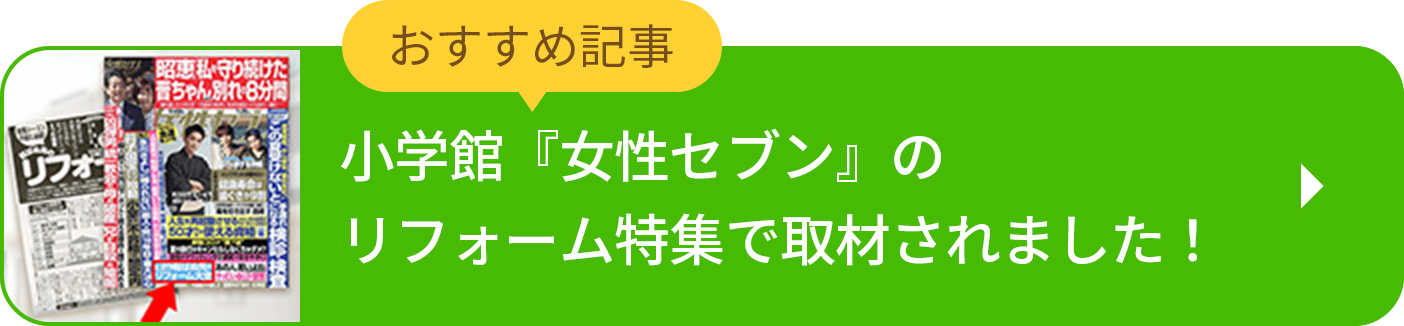木造住宅は音漏れがどうしても気になってしまいます。楽器を使う場合や、集合住宅だった場合はなおさらでしょう。ここでは初めて木造アパートに住む方には、どの程度音漏れがするものかといった、音漏れの程度についてを。既に木造住宅に住んでいらっしゃる方には簡単にできる防音対策と、リフォーム会社にお願いする本確的な防音対策についてそれぞれご説明いたします。
目次
1.木造アパートはどの程度音漏れするの?
木造アパートに住む場合に気になるのが、近所の音漏れについてです。気になるかならないかは本人の主観に依存する部分も大きいのですが、実はアパートのつくりによっても聞こえ方はだいぶ変わってきます。 次の表は日中と夜間で近隣住民からどの程度の音量が聞こえるかを目安として示したものになります。
| 騒音レベル | デシベル | 身近な例 | 日中聞こえる | 夜間聞こえる |
|---|---|---|---|---|
| 極めて うるさい |
120デシベル | ドラム音 | ○ | ○ |
| 110デシベル | 車のクラクション | ○ | ○ | |
| 100デシベル | 電車通過時のガード下 | ○ | ○ | |
| 90デシベル | カラオケ店 | ○ | ○ | |
| 80デシベル | ピアノ音 | ○ | ○ | |
| うるさい | 70デシベル | テレビの音 | ○ | ○ |
| 60デシベル | 水を流す音 | ○ | ||
| 普通 | 50デシベル | 冷房の吹き出し音 | ||
| 40デシベル | 昼間の住宅地 | |||
| 静か | 30デシベル | ささやき声 | ||
| 20デシベル | 時計の針 |
木造の場合は日中でも隣の部屋のテレビの音はかすかに聞こえてくるかもしれません。夜に布団に入っている状態であれば、隣の部屋で水を流す音もかすかに聞こえることもあるかもしれません。どの程度の音が気になるかは人それぞれかもしれませんが、木造アパートを選ぶ際の一つの基準にしていただければと思います。
また同じ木造であっても、造りや防音の状態によって聞こえ方は異なってきますので、その点は注意が必要です。気になるようであれば下見に行った際、実際に音を聞いてみるのが良いでしょう。
2.お金を掛けずに自分で出来る防音の工夫
賃貸住宅なので防音対策が勝手にはできないケースや、あまりお金を掛けずにやりたいという方も多いかと思います。近所の騒音を防ぎたいという場合もあるでしょうし、逆に近所に迷惑を掛けないようにしたいという場合もあるでしょう。
木造住宅では騒音を完全に無くすのは難しいですが、少しでも騒音を防ぐためにご自身で出来る方法をご紹介致します。
2-1家具の配置を見直す
家具の配置を見直すことで防音に効果があるケースがあります。簡単にできるものをご紹介致します。
TVやスピーカーなど音の出る家電は壁から離す
音は壁を伝って響きやすくなります。もし可能であれば壁から50cm以上離すとよいでしょう。
壁際には大きめの本棚やタンスを置く
本棚やタンスが音を遮断する役割を担ってくれます。さらに、本棚や棚に荷物がある方が防音の効果は高まります。
2-2.ちょっとしたものを敷く
何かを敷くことで音が響くのを防ぐことができるようになります。特に音が気になる部分を見つけて試してみてください。
スピーカーの下に布を敷く
音が出る家電はどうしても接地面から音が伝わってしまいます。布を敷くだけでも騒音がかなり解消されます。
床にカーペットを敷く
防音用のカーペットでなくとも、普通のカーペットが1枚敷いてあれば下に響く音は軽減されます。
冷蔵庫・洗濯機の下に防音ゴム
実は、一人暮らし用のコンパクトタイプほど音がうるさかったりするものです。防振ゴムを敷くことによって振動音自体を軽減させることが出来ます。
椅子の脚にカバーを付ける
椅子は日常的に出し入れをするので、思った以上に騒音の原因になっています。脚にカバーを取り付けるだけで騒音を防止することが出来ます。
2-3.その他の工夫
カーテンを利用する
本格的に防音したい場合は遮音カーテンを購入するのも一つの方法です。遮音カーテンでなくとも、お持ちのカーテンを利用すれば、音が直接出入りするのを防ぐ効果があります。
窓ガラスに何かを張る
見た目を気にしないのであれば、包装に使うビニールのプチプチを窓に貼るという方法もあります。もしくはガラスに貼るだけの防音フィルムを利用するのもよいでしょう。窓、特に通常のガラスは騒音が入ってきやすいので、気になる方は対策を取られるとよいでしょう。
ドアに隙間テープをはる
窓やドアに防音をしても、隙間から音が出入りしてしまうことがあります。音漏れする隙間にテープを張ることで、隙間からの騒音を減らすことが出来ます。閉めるときにちょっと力が必要なくらいの厚さのテープの方が、防音の効果は高いといえます。
いかがでしたでしょうか?簡単に取り組めるものばかりなので、出来るところから試してみるといいかもしれません。
3.リフォームで出来る防音対策
3-1.防音リフォームの基礎
防音を考える際にまず知っていていただきたいことは、「騒音の原因によって対策方法は全く違う」ということです。例えば以下の点について少し考えてみてください。
- 自分が出す音を防ぎたいのか、入ってくる音を防ぎたいのか
- 建物の中から聞こえる音か、外から聞こえる音か
- どのような種類の音か
- 一戸建てか、集合住宅か
これらを考えるだけでも、「防音」に対するとらえ方がだいぶ違ってくるのではないでしょうか?これらを考えたうえで、現状のお部屋にあった防音方法を考えてみてください。
3-2.床の防音
床の防音に関しては、まずは防音カーペットを敷くことから考えましょう。少しお金はかかりますが、自分でも出来る比較的手軽な内容になります。
防音カーペットには「タイルカーペット」「コルク」「防音ラグ」の3種類があります。防音効果と価格帯は以下の通りです。
タイルカーペット


部屋の形に合わせてカット出来るので、使いやすく、汚れてもその部分だけ取り替えることが可能です。値段の安価なものもありますが、防音効果を考えるのであれば専門店で相談しながら決めるとよいでしょう。自分でできる防音アイテムの中ではお勧めです。
コルク


振動は防ぎますが、吸音効果は少ないのがコルクの特徴です。
小さいお子様がいらっしゃる場合はケガ防止対策としても利用しやすいです。汚れ防止という点からも小さいお子様がいらっしゃるご家族には人気となっています。
ラグ


サイズに合わせて気になる部分にだけ引くことが出来るのがラグのメリットです。吸音性も高いので、オーディオ等の音にも効果があります。 防音カーペットでも足りない場合は、カーペットと床の間に遮音・防音マットを敷きましょう。
防音マットは硬いゴムのような手触りで、樹脂製のマットになります。吸音性があるので空気中を伝わる音も軽減するうえ、振動自体も軽減します。ただ、効果は高いのですが、床と防音カーペットの間に敷く場合、色移りやにおいを気にする方もいらっしゃるようです。
3-3.壁の防音
壁は厚みがあるせいで、壁から音が侵入してくるというのはそれほど問題にはなりません。壁自体からの侵入より、換気口やドア、窓の開閉口からの侵入が多いでしょう。簡単にできる防音としては、防音ボードを利用する事をお勧めしますがそれ以外の方法としては、少し手間がかかりますが防音地下材と防音換気口を利用する方法があります。
防音地下材は、防湿遮音シートや遮音下地パネルなどを使って壁の防音対策を行いますので壁自体にリフォームが必要となります。実施の際は専門家に相談するのが良いでしょう。 また防音換気口を用いる場合は、換気口などの開口部に防音効果のある換気口を設置します。
いづれも費用と効果兼ね合いがあるので、どの方法を取り入れるかは専門家に相談することをおすすめします。
3-4.窓の防音
窓から出入りする音はガラスよりもサッシの隙間からの方が多く、音漏れについても同様です。そのためガラスを交換するだけでは防音対策としては物足りません。
窓はガラスとサッシの組み合わせで構成されているので、両方の防音効果を高めることが有効です。より有効なのがサッシの隙間対策ということになります。ここでは2種類の窓リフォームの方法についてご説明いたします。
窓の交換


工事が簡単で壁を壊したりすることなくリフォームを行うことができます。既存の窓の交換になりますので、2階の窓でも大掛かりな作業が不要です。窓自体の種類も豊富なので、現在の生活スタイルに合わせて自由に選ぶことができるというメリットがあります。 防音効果は二重窓にした場合よりは落ちるものの、簡単かつ窓際の美しさにもこだわりたいような場合はお勧めです。
内窓の増設


窓の防音に最も効果的なのは内窓を取り付けて二重窓にすることです。室内の壁紙や外壁に影響を与えずにリフォームができるため、取り付け自体も簡単に行うことができます。 デザイン性の観点では、前述した防音窓への交換の方がすっきりとしますが、防音効果自体を重視されるならば内窓を取り付けるという選択をお勧めいたします。
4.防音室を作るならば
本格的に防音対策を考えるのであれば、部屋自体を防音室にしてしまうというのが最も適した方法になります。費用はどの程度の防音対策を採用するかによっても異なります。以下の金額は目安となりますので参考にしてください。
- 防音書斎:100万~
- ホームシアタールーム:180万~
- ピアノ防音室:230万~
- レコーディングスタジオ:330万~
防音室を作るには部屋の現状を調査し、その部屋と防音の目的に沿った対策をすることが大切になります。防音はリフォームの中でも特殊な部類にあたりますので、防音を専門に扱う会社にお願いするのが安心です。
5.まとめ
木造住宅は良い面もあるのですが、やはり防音面では気になることが多いのも事実です。防音を施すのであれば、まずは音漏れの箇所や種類を判断することが最も重要になります。音漏れの原因をしっかり把握していなければ、せっかく施した防音対策自体も効果が限定的になってしまいます。
本格的な防音を考えた場合は、専門の業者にお願いするのが安全で効果的です。それぞれの状況にあわせて適切な防音対策を行いましょう。
(防音リフォームの関連記事)
全ノウハウまとめ
防音リフォームを成功させる全ノウハウまとめ
その他関連記事