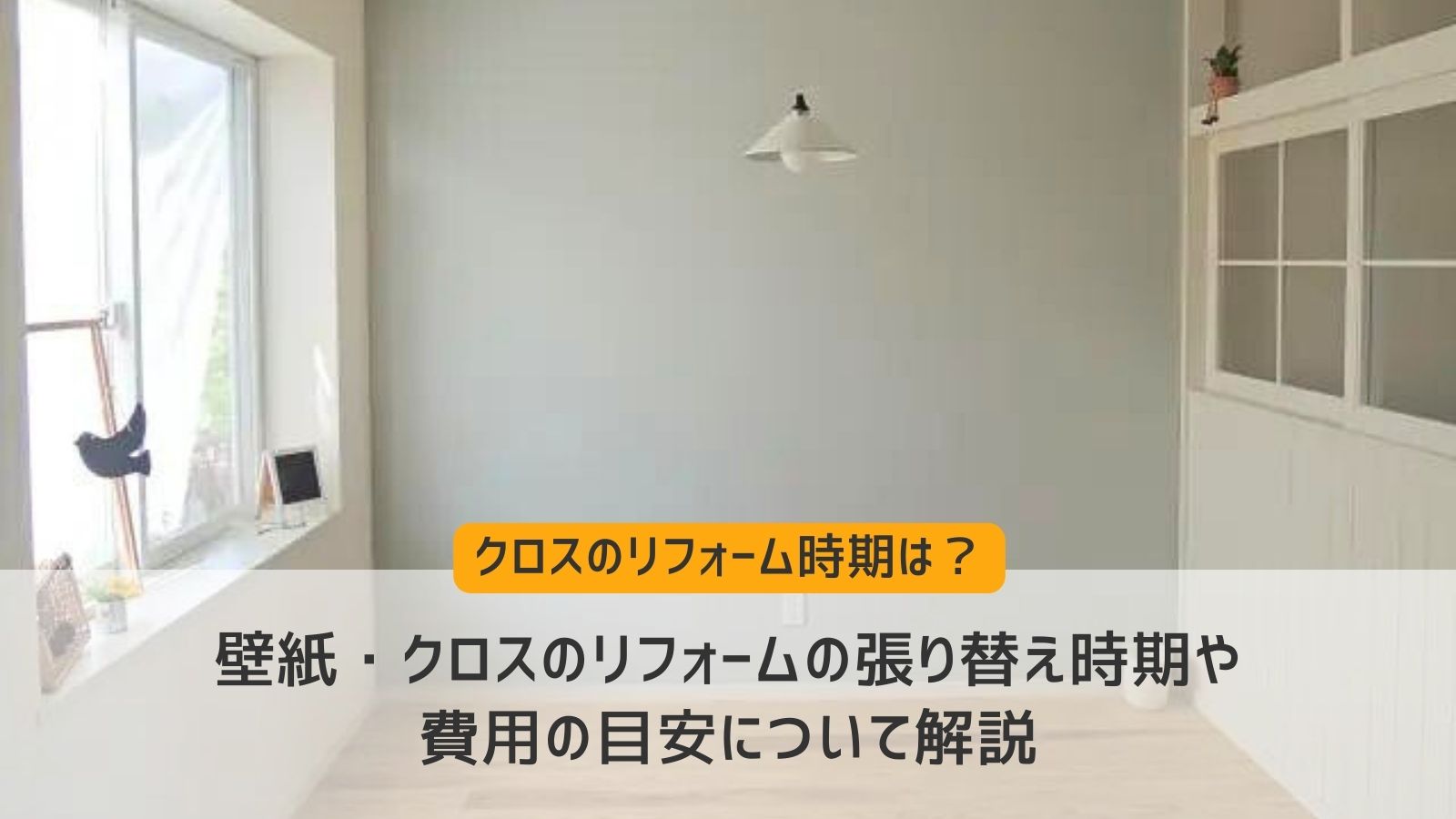
壁の汚れやキズが目立ってきたら、壁紙(クロス)のリフォームつまり張り替えの時期かもしれません。
しかし、壁紙(クロス)の張り替えの時期や費用についてよくわからなず、張り替えをするかどうかなかなか決められない人もいると思います。
そこで、この記事では壁紙(クロス)のリフォームの時期や費用の目安について以下の内容を説明します。
- 壁紙(クロス)のリフォームのタイミング
- 壁紙を長持ちさせる5つの秘訣
- 壁紙(クロス)の種類と特徴
- 壁紙の張り替えと費用
- 壁紙のリフォームのポイント・注意点
壁紙(クロス)のリフォーム時期や費用のことを知れば、タイミングを逃して無駄な費用をかけなくて済みます。そして、適切な時期と費用でリフォームができるでしょう。
>>実際の見積もりから算出した壁紙(クロス)リフォームの費用相場をチェック!
1.壁紙(クロス)のリフォームのタイミング
壁紙(クロス)の張り替え時期は耐用年数だけではなく、壁紙の劣化具合によっても変わってきます。
ここでは壁紙(クロス)のリフォームのタイミングについて細かく説明します。
1-1.壁紙の耐用年数
壁紙の耐用年数は約10年と言われています。しかし、壁紙の材質や扱い方、普段のお手入れ、喫煙などで大きく変化します。
早ければ5年ほど、長持ちさせれば20年ほどでリフォームのタイミングになります。後ほど、壁紙を長持ちさせる方法も説明しますので、参考にしてください。
1-2.壁紙の色褪せ、変色
壁の色あせや変色が目立ってきた場合はリフォームのタイミングです。リフォームが必要になる変色の原因としては、このようなものが考えられます。
- 経年焼け(日焼け)した
- たばこのヤニがついた
- 壁掛けや額縁などからの色移りした
- 壁紙を張った際に、接着剤のふき取りが不十分だった
これ以外の場合は単なる汚れのことが多く、年数が経っていなければ、中性洗剤や壁紙専用の洗剤で落とせることが多いです。
1-3.壁紙の剥がれ
壁紙に剥がれや浮きが起きた場合もリフォームが必要です。原因として考えられるのは、乾燥や結露による壁紙の収縮です。
湿気を含めば壁紙が伸び、乾燥すれば縮むことを繰り返すことで剥がれが起きるわけです。特に窓の近くやキッチン、浴室の壁紙ははがれやすい場所です。
他の原因としては、壁紙を貼る前の掃除が不十分だったり、接着剤が下地にしっかりと貼りついていなかったりといったことが考えらえます。また接着剤の劣化が剥がれの原因になっていることもあります。
年数がそれほど経っておらず、剥がれが軽度な場合は、その部分を補修することで対処できます。しかし、そのままにしてしまうと、剥がれた部分が広がってしまったり、下地が傷んでしまうので注意が必要です。
1-4.壁紙の劣化など
壁紙の劣化で最も大きな原因は収縮です。壁紙は時間とともに縮んでいく性質をもっています。
壁紙にとっての環境が良くない場合は早ければ1年ほどで縮んでしまい、継ぎ目が開いてしまうことがあります。
経年劣化のため、表面のケバ立ちやたわみ、シワなどが目立ってくることがあります。また、壁紙の防水性能や消臭性能が薄れるという場合も、張替えのリフォームが必要になります。
1-5.その他の要因
その他で壁紙のリフォームを考える要因としては
- カビの発生
- 壁や天井のヒビ
- 壁紙の継ぎ目に汚れがたまってきている
などがあります。
特に、湿気が強い部屋の壁紙は表面にシミのようなカビが発生してしまうことがあります。また、カビが壁紙の下地から発生している場合は、壁紙を張り替えるだけではカビはなくなりません。
専門の業者に依頼して下地からリフォームすることを考える必要があります。壁紙のカビには十分注意しましょう。
1-6.壁紙が寿命を超えたらどうなるか
壁紙は石膏ボードなどの壁に接着剤で貼りつけるのが一般的です。
耐用年数を大きく超えてしまっていたり、汚れや剥がれをほおっておくと、壁紙だけでなく接着剤が劣化してしまいます。そのため、壁紙の張り替えるときにきれいに剥がすことができなくなります。
また、壁紙を剥がす際に下地の表面まで剥がしてしまうと、下地の補修や交換まで必要になってしまいます。
そうなると、工期が余分にかかり、費用も思った以上に高額になることがあります。耐用年数を過ぎたり、劣化や汚れや傷などが目立ってきたら、早めのリフォームを考えるといいでしょう。
2.壁紙を長持ちさせる5つの秘訣
壁紙を長持ちさせることができれば、壁紙の寿命を伸ばせます。以下に壁紙を長持ちさせる秘訣を5つ紹介します。
2-1.傷をつけない
壁紙の表面に傷がついてしまうと補修は難しいものです。
傷をつけないためにはテーブルやソファーなど家具の角を壁から離し、壁紙に当たらないようにします。また、家具を壁につけてしまうと、色移りしてしまうことがあります。
ペットによる傷が気になる場合は表面強化壁紙などを使うことも検討しましょう。
2-2.換気する
壁紙の汚れの原因で代表的なものは、たばこの煙や料理の油煙です。これらは壁紙を黄色く変色させたり、壁紙にニオイをつけてしまったりします。
また、冬などに湿度が高いと結露が発生しやすくなり、壁紙のシミや剥がれ、カビ発生の原因となります。換気扇や除湿器などをこまめに使い、部屋の空気をしっかり換気しましょう。
2-3.直射日光を避ける
壁紙が直射日光にさらされていると、紫外線の影響で変色したり傷んだりすることがあります。
直射日光が当たる部屋はカーテンやブラインドなどで直射日光が当たらないようにしましょう。また、窓ガラスに紫外線(UV)カットのフィルムを貼る方法もあります。
2-4.高温多湿を避ける
ストーブなどの暖房器具の熱風が壁紙に直接当たらないようにします。また、日当たりの悪い部屋で湿気の多い環境が続けば壁紙に悪い影響を与えます。
2-5.汚さないようにする
汚れの種類によっては簡単に落ちないことがあります。また、汚れを無理に落とそうとすると壁紙を痛めてしまうことにもなります。
汚れ防止の機能のある壁紙を利用するか、部分的に汚れ防止シートを貼る方法もあります。
3.壁紙(クロス)の種類と特徴
壁紙(クロス)にはいくつかの種類があります。ここではそれぞれ素材の違いや特徴、メリット・デメリットなどについて説明します。
3-1.ビニールクロス
ビニールクロスは最も普及している壁紙です。
塩化ビニール樹脂を主原料とするビニールシートに紙を裏打ちして作られたシートです。プリント柄や織物柄、立体感を出したものなどさまざまなデザインのものがあります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 価格が安く、施工費も抑えられる | 化学物質のためアレルギーの心配がある |
| 耐水性があり、汚れを拭き取りやすい | 独特なニオイがある |
| 防臭・抗菌・防カビなどの機能も豊富 | 通気性・調湿性が弱い |
3-2.織物クロス
織物クロス(布クロス)の素材は自然素材(木綿・麻・絹など)や化学繊維(レーヨン・ポリエステルなど)です。
そして、それらを使った織物や編み物、不織布などを紙で裏打ちしたクロスが織物クロス(布クロス)と呼ばれるものです。高級感や重量感があり、特に自然素材にこだわりたい場所に向いています。
織物クロス(布クロス)の表面は水拭きできないので、はたきやブラシを付けた掃除機でホコリを取ります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 通気性・調湿性がある | 高価で施工費もかさみやすい |
| 自然素材なのでアレルギーにも安心 | 汚れが落ちにい・キッチンには不向き |
| 丈夫で破れにくい | 摩擦に弱い |
3-3.紙クロス
紙クロスは、和紙やパルプなどの原料を素材にしています。その他に非木材紙を原料とした特殊紙や、表面をフィルム加工した合成紙を素材にしたものもあります。
その素材の紙に印刷や型押しをして、色や柄をつけて紙で裏打ちをします。柄が楽しめるプリント加工や凹凸のあるエンボス加工などが施してあります。
紙クロスは欧米でよく使用されているので、輸入物が多く色や柄が個性的なものが多いのが特徴です。また撥水加工がされているものもありますが、一般的には水拭きを避けた方がいいでしょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 通気性・吸音性がある | 高価で施工費もかさみやすい |
| 欧米風の個性的なデザインがある | 水や油に弱くシミになりやすい |
| 自然素材なのでアレルギーにも安心 | 摩擦に弱い |
3-4.その他
その他の壁紙(クロス)としては薄い木材やコルクを紙に張り付けた木質系壁紙や、珪藻土や漆喰を表面に打ち付けた無機質系のクロス、合成樹脂を原料としたオレフィン壁紙などがあります。
| 壁紙(クロス)の種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 木質系壁紙 | 木やコルクの素材感 | 高価・一般的には水に弱い(耐水加工のものもある) |
| 無機質系のクロス | 防火性がある | 塗り壁に比べて調湿性・吸音性は期待できない |
| オレフィン壁紙 | 汚れ、キズに強い | 高価で施工費もかさみやすい |
3-5.クロスの選び方
クロスの選び方として
- デザイン、グレード
- クロスの価格・施工の費用
- 機能性(汚れ防止・防菌・防カビ・防臭など)
- 部屋に合わせた材質や色、柄
などを考えて選ぶことになります。
例えば、トイレや脱衣所などは防カビ効果のあるクロスを選ぶといいわけです。また、玄関やリビング、階段などは人通りが多いので、強度がありキズが付きにくいクロスがいいでしょう。
また、クロスを選ぶ際の注意点としては
- サンプルブックで実物を確認する
- 床の色や素材に合わせる
- 家具の色に合わせる
があります。実際に壁紙を見て確認することと、床や家具とのバランスを考えて壁紙(クロス)選ぶことになります。そのためには取り扱う種類が豊富なメーカーなら適したクロスを選びやすいでしょう。
4.壁紙の張り替えと費用
ここでは壁紙(クロス)の張り替え工事の流れと費用の目安について説明します。
4-1.張り替え工事の流れ
1室の壁紙・クロスの張り替え(天井・壁)にかかる工期は約1~2日です。下地の補修が必要な場合は2日程度必要になるようです。
全室で2LDKや3LDKの場合は約1週間、4LDKの場合は1週間~10日程度かかります。
工事の流れは以下のようになります。
- 工事前の確認(工事手順、施工箇所、壁紙の確認)
- 家具を移動したり、養生シートで覆う
- コンセントやスイッチ、照明などを取り外す
- 古い壁紙・クロスを剥がす
- 下地の処理や補修
- 新しい壁紙を貼り付ける
- 仕上がりの確認、後片付けなど
壁紙張り替え工事で重要なのは、こまめな片付けと下地づくりだと言われています。
また、工事終了直後に問題がなかったとしても、後日剥がれやしわが生じて補修が必要になることもあります。中には工事後の補修が有料の業者もあるので注意が必要です。依頼前に確認して、アフターサービスや工事保証がしっかりした業者に依頼しましょう。
4-2.張り替え費用について
壁紙の張り替えにかかる費用としては、壁紙の料金以外に
- 養生代(家具などを養生シートで覆う作業代)
- 下地の処理費用(壁紙を剥がした後、下地を整える作業代)
- 廃材処理費(古い壁紙の処理代)
- 荷物の移動費(あらかじめ家具を移動しておくと節約できます)
一般的に6帖・1室、天井と壁の壁紙(クロス)の張り替えで、約5万円から、3LDKの居宅全体の場合は約40万円からになります。壁紙の種類や下地処理の有無や規模によって費用は変わってきます。


5.壁紙のリフォームのポイント・注意点
自分で張り替える自信があればDIYで壁紙をリフォームする手もあります。
確かにリフォーム業者に依頼するよりも費用を抑えることができます。ただし、コンセントやエアコン、窓の周りの貼り方など結構難度が高いものです。
ここでは壁紙のリフォームのポイントや注意点について、DIYと業者それぞれについて説明します。
5-1.DIYで張り替えるには
壁紙(クロス)をDIYで張り替えるのはもちろん可能です。最近はDIYで張り替える人も多くなっています。ホームセンターによっては実施に貼ってみることもできるようです。
しかし、気を付けなければならないことがあります。それは、壁紙を張り替えていいのは、基本的に戸建て住宅(持ち家)や分譲マンションなどの「自己所有」の物件です。
賃貸物件の場合は許可なく壁紙を張り替えることはできません。オーナーや管理会社に許可を得て張り替える必要があります。また、賃貸の契約書の禁止事項に壁のリフォームが含まれている場合があるので、事前に確認する必要があります。
また、賃貸の場合は既存の壁紙にシールタイプなどの壁紙を貼って退去時に剥がすという方法もあります。
DIYで壁紙(クロス)を張り替える場合、失敗してしまうことも少なくないので、事前に情報を集めて、しっかりと知識をつけてから始めましょう。
DIYで張り替える手順
壁紙(クロス)の張り替えの手順については初めに道具をそろえてクロスを購入すること以外は「4-1.張り替え工事の流れ」の内容と同じです。壁紙の施工道具セットなども販売されていますし、脚立などの足りない道具は必ず事前に購入しておきます。
まずは寝室や書斎など来客が入らない部屋や、一部分で壁紙を張り替えて経験を積み、徐々にその部屋全体や他の部屋にチャレンジしていくのもいいかもしれません。
DIYでの注意点や失敗例は
古い壁紙を剥がす際にうまく剥がない場合は、下地にシーラー処理や、パテ埋めなどをしたりする必要が出てきます。それもDIYで行うことはもちろん可能です。
ただし自信がない場合は、壁紙の一部を剥がしてみて剥がれ具合を確認し、問題があれば業者に依頼することもできます。また、シールタイプの壁紙を既存の壁紙の上に貼り付けることでリフォームすれば失敗が少なくなります。
失敗例としては「張り替え後に表面に凹凸ができた」「しばらくしたら剥がれがでてきた」「柄物のクロスの継ぎ目がズレて見栄えが悪くなってしまった」「思ったより難度が高く、時間がかかり、仕上がりも良くなかった」などがあります。それらはDIYの楽しみにはなりますが、自信がなければリフォーム業者に頼んだ方がいいかもしれません。
5-2.業者選びのポイント
壁紙の張り替えをリフォーム業者に依頼する際、業者選びのポイントなどについて説明します。費用に関しては事前に相場を調べておくと安心です。もちろん業者に依頼すると費用はDIYよりもかかりますが、その分メリットもあります。
業者による張り替え
業者に張り替えを依頼するとDIYに比べて以下のようなメリットがあります。
- 工期が短く、仕上がりがきれい
- 相談に乗ってくれたり、アドバイスをしてくれる
- 大量に出るゴミの処分をしてくれる
- 施工後のアフターサービス(業者による)
などでしょうか。業者に依頼する部分とDIYで行う部分を区別してリフォームすることもできます。また、まず業者に一部屋張り替えてもうなどして技術を学び、その後DIYでやってみる手もあります。
業者選びのポイント
必ず複数の業者から見積もり(相見積もり)をとります。少なくとも3社から相見積もりを取って比較しましょう。また、比較サイトで一括して見積を取る方法もあります。見積書でよくわからない項目があったら必ず質問し、追加料金の有無、アフターサービスの内容などしっかりチェックしておきます。
そして、実績があり、担当者とも相性が合う業者を選びましょう。


6.まとめ
壁紙(クロス)の寿命、リフォームの時期や費用の目安、壁紙の種類などについて説明しました。日々のお手入れで壁紙を長持ちさせるのも大切です。また壁紙の変色や劣化を放置しておくと下地を痛めてしまいリフォームの工期や費用が余分にかかってしまいます。
この記事を参考に最適なタイミングで、しっかりした業者を選んで壁紙・クロスのリフォームをしましょう。
(壁紙・クロスリフォームの関連記事)
全ノウハウまとめ
壁紙クロスの張り替えを成功させる全ノウハウまとめ
その他関連記事
- 壁紙(クロス)張替えの業者選び|おすすめの依頼先や探し方のポイント
- クロス(壁紙)の張替え単価|リフォーム費用が変わる要素と安く抑えるコツ
- 【プロが教える】マンションの壁紙張替え費用とリフォーム事例
- 壁紙(クロス)張り替えの費用相場はいくら?安く抑えるコツや張り替え事例も紹介
- 壁紙(クロス)の種類。素材の特徴とリフォームに向いている場所を紹介
- 除湿機の電気代は高い?エアコンとの比較と節約方法
- 内装フルリフォームの費用は?パターン別・築年数別の相場も解説
- 部屋の湿気がひどい原因は?すぐにできる対策やリフォームを紹介
- 砂壁リフォームの方法と費用相場|リフォーム会社の選び方も解説
- 腰壁とは?DIYできる?おすすめの導入場所、メリット・デメリット
壁紙・クロスリフォームの費用と相場
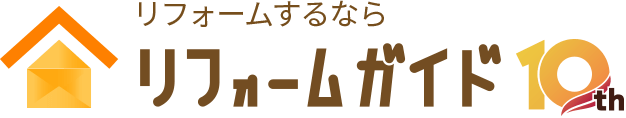








 なら
なら

