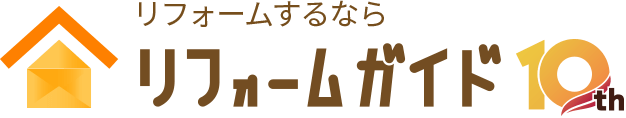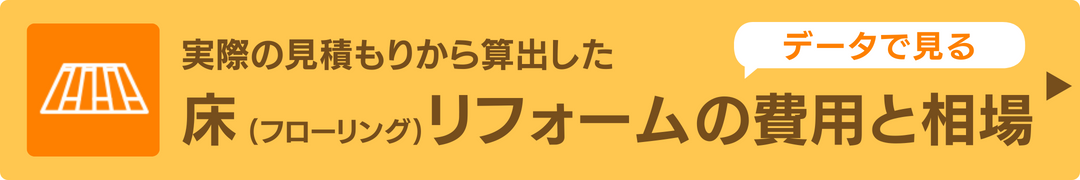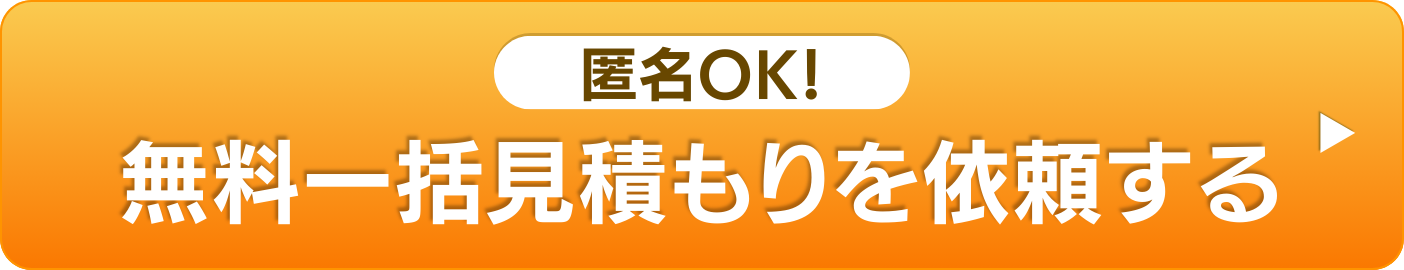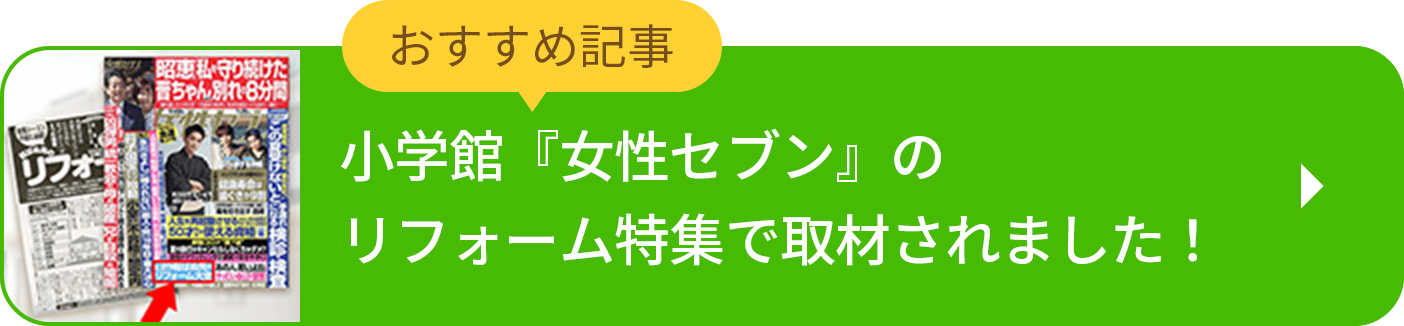床が軋んだり、鳴ったりするなど床の劣化が目立つようになったときや、傷やシミが気になってきたときはフローリングの張り替えの時期かもしれません。また、それ以外でもフローリングを張り替えるといい場合があります。
「フローリング張り替えの時期を知りたい。」
「フローリング張り替えの注意点について知りたい。」
「フローリングの張り替え費用が心配。」
「フローリングの張り替えが自分でできるのか知りたい。」
こういった悩みがある方も多いはずです。
この記事ではフローリングの張り替えを考えている方のために、以下の内容で説明します。
- フローリングの種類や寿命について
- フローリング張り替えのタイミング
- フローリングの張り替え方法
- 張り替えの費用の目安
上記のことを知れば、適切なタイミングや方法でフローリングの張り替えができるヒントとなるでしょう。
目次
1.フローリングについて知っておこう
まずはフローリングについて、その種類や寿命を決める要因、耐用年数について説明していきます。
1-1.フローリングの種類
フローリングは木材でできた床材です。フローリングは大きくわけて「複合フローリング」「無垢フローリング」の2つの種類になります。
ここでは、それぞれの特徴やメリット・デメリットについて詳しく説明します。
複合フローリングについて
複合フローリングは合板フローリングとも呼ばれています。複数の薄い木板を張り合わせた合板を「基材」として、その表面に天然木の板や木目調のシートなどの「化粧材」を貼ったものです。工事期間を短くしたい場合や防音性や耐水性などの機能性を持たせたい場合におすすめです。
複合フローリングは床板の種類や厚み、仕上げ方によって費用が変わります。耐久性のある床材や無垢のようなデザインのものほど費用がかかります。また、防音性の機能を持つ製品も多いので、マンションなどの集合住宅でのリフォームにはおすすめの床材です。
複合フローリングのメリット・デメリットは以下のようになります。
複合フローリングのメリット
- 色やデザインのバリエーションが豊富
- 木目や色が均等で、反りや縮みがでにくい
- 防音性や水ぬれに強いなど機能性の高いものが選べる
複合フローリングのデメリット
- 無垢フローリングに比べて寿命が短い
- 深い傷の場合は修復が難しい
- 天然木特有の風合いが足りない
無垢フローリングについて
無垢フローリングは単層フローリングと呼ばれることもあります。天然木から切り出した「一枚板」を材料としています。そのため、素材そのものの香りが楽しめるという特徴があります。
また、無垢フローリングは調湿効果もあり健康的とも言える素材なのですが、防音性があまりなく、マンションなどの集合住宅では使用できない場合があります。
マンションの場合、管理規約に違反しないか確認してから無垢フローリングを選ばないといけません
無垢フローリングのメリット・デメリットをまとめると以下のようになります。
無垢フローリングのメリット
- 自然素材ならではの温もりや風合いがある
- 経年劣化がかえって味わいに変わる
- 調湿効果や断熱効果が期待できる
無垢フローリングのデメリット
- 伸び縮みで、床が変形したり軋みやすい
- 傷が付きやすく、水に弱いためシミになりやすい
- 費用が高め
2つの床材について、以上のことを表にまとめてみます。
| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 複合フローリング |
|
|
| 無垢フローリング |
|
|
1-2.フローリングの寿命を決める要因
フローリングの寿命は一般的には10年~20年といわれています。もちろん、気候や手入れなどによって大きく変動します。
ここではフローリングの寿命を決める要因について説明します。
フローリングの日焼け
南向きの部屋や日当たりの良い住まいは、生活するには良い環境かもしれません。しかし、床にとっては過酷な環境なのです。
直接日光がフローリングに当たると、紫外線によって日焼けが生じてしまいます。そして、フローリングが日焼けしてしまうと黄変や白化といった色あせや、ひび割れが発生してフローリングの寿命を縮める原因となってしまいます。
また、費用や手間がかかってしまいますが、窓などに紫外線をカットする効果が大きなガラスを使用したり、紫外線(UV)カットフィルムを貼ったりすることでフローリングの日焼けをある程度は防止することができます。
フローリングの汚れやシミ
フローリングは基本的に水分に弱く、ぬれた雑巾でふき掃除をした場合でさえ、その水分が劣化の原因になることがあります。特に、キッチンやトイレ、洗面室など水を多く使う場所の周辺では水分による劣化がより多く見られます。また、ペットの尿に含れるアンモニアは粒子が細かくフローリングにしみ込みやすいため、においやシミで劣化してしまう場合もあります。
そして、水分を吸収したフローリングは腐食などで変色したり、浮き上がったりしてしまいます。
その他
椅子を引いたときや、ものを落としてしまった時に付く傷、またペットの爪などによる傷などもフローリングの劣化の原因になります。ただし、生活していく上で、床に傷がつくのは仕方のないことかもしれません。しかし、付いた傷がさらに深い傷になったり、そこから水分が入り込んでしまったりして床の寿命が短くなるので注意が必要です。
1-3.フローリングの耐用年数
フローリングの耐用年数は、床材や下地の状態によって変わってきます。床材の劣化の症状が現れてくるのは一般的に10年程度だと言われています。そしてフローリングの張り替えは15年~20年程度で行われることが多いようです。
2.フローリングを張り替えるタイミング
ここではフローリングの張り替えのタイミングについて詳しく説明します。
2-1.フローリングの劣化
フローリングが劣化して、床のへこみや軋み、沈みなどを感じた時はリフォーム(張り替え)のタイミングです。また、床に傷や痛み、色褪せが目立ってきたときもリフォームの検討時期です。
ところで、床鳴りや軋み音、たわみなどを感じた場合に床材が痛んでいるのではなく、床下の方に何らかの異常があることが考えられます。その場合は新しいフローリングに換えてもすぐに同じような不具合が現れてしまいます。床下の異常については、その原因をつきとめることが必要になるため、専門の業者に状態を確認してもらい適切な処置を行うことになります。
2-2.劣化以外で張り替えるタイミング
フローリングの張り替えは劣化が原因で行うだけではありません。以下のような場合にも張り替えを行うことが考えられます。
- 家族構成やライフスタイルが変わることにより、畳の部屋(和室)をフローリングの 床(洋室)に変える
- 部屋のインテリアを大きく変えたので、それに合わせてフローリングも張り替える
- 壁紙の張り替えを行った際に、フローリングの劣化が目立ってしまう
- ペットを飼うようになり、汚れや傷に強いフローリングに張り替える
このように、フローリングの張り替えのタイミングは劣化以外にいろいろとあります。
3.フローリングの張り替え方法
フローリングを張り替える方法としては「重ね張り」と「張り替え」の2つの工法のどちらかで行うのが一般的です。それぞれについて詳しく説明します。
3-1.重ね張りとは
重ね張りとは既存の床材の上に接着剤などで新しい床材を貼り付ける工法です。ただし、既存の床材が腐食や軋み、沈みなどの劣化をしていないことが前提です。
また、下地が痛んでいないことを前もって確認しておく必要があります。もし、下地が痛んでいると、張り替えても軋みや沈みが解決できないことが起こります。
重ね張りは、はがし作業が不要なため工期も短くなり、費用も抑えることができます。さらに重ねて貼ることによって床の強度が増すことにもなります。
重ね張りの工法は、張り替えの工法のように床を解体する必要がありません。さらに、既存の床材を剥がすときの音やホコリがほとんどなく、1部屋なら当日中に施工することができます。
ただし、既存の床の上にさらに重ねて床材を張り付けるために、施工前より床が厚くなります。事前に調べておかないとドアの開閉がしづらくなり、ドアなどの高さの調整が必要になることがあります。
3-2.張り替えとは
張り替えとは既存の床材をすべて剥がして、下地は交換せずに新しい床材に貼りなおす工法です。床材をすべて剥がすため工期が長くなり費用もかかりますが、下地の確認ができるというメリットがあります。
経年劣化やシロアリの影響で下地が痛んでしまっていれば、床を新しくしてもすぐに軋みや沈みが生じてしまうことになりかねません。特に、長年経った住宅の場合は床の下地が痛んでいることが多いので、場合によっては床の補修ができるのもメリットだと言えます。
また、既存の床材を剥がしてから新しい床材に張り替えるので、床の高さはほとんど変わることがありません。
張り替えは和室から洋室にするリフォーム、クッションフロアをフローリングにするリフォームなど、床材そのものを変更するときに適した工法です。また、前回の張り替えから10年以上経っていたり、床鳴りや軋み音がしたりする場合も、張り替えの工法によるリフォームがおすすめです。
| フローリングの張り替え方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 重ね張り |
|
|
| 張り替え |
|
|
3-3.フローリングをDIYで張り替えるには
フローリングのリフォームは業者に依頼するのが一般的ですが、DIYでもリフォームすることができます。
最近はDIYの初心者でも扱えるような床材があります。それは裏面の滑り止め加工やシールなどにより、カッターで切って既存の床の上に置くだけのものです。それなりに手間はかかりますが、施工費用がいらないため検討してもいいかもしれません。
本格的にDIYでフローリングを張り替えるのなら「重ね張り」がいいでしょう。ただし、決して容易ではなく、工具を買い揃えるかレンタルにしたり、施工の方法を調べたりと随分な手間や時間、費用がかかります。それは覚悟をもって行う作業になると思います。
また、「張り替え」で行う場合や床暖房へリフォームする場合は相当難度が高いので、プロに任せた方が安心です。
4.張り替え費用の目安
床材の張り替え費用は、張り替える前と後での床材の材質、工法や床面積などで変わります。ここでは一般的な費用の目安を表で示します。
広さと工法による、フローリングの張り替えの費用の目安は以下のようになります。
| 広さ | 重ね張り | 張り替え |
|---|---|---|
| 6畳 | 6~14万円 | 9~18万円 |
| 8畳 | 8~18万円 | 10~20万円 |
また、張り替える前の床材の違いによる、6畳での費用の目安は以下のようになります。
| 張り替える前の床材 | 複合フローリング | 無垢フローリング |
|---|---|---|
| フローリング | 12~16万円 | 15~20万円 |
| クッションフロア カーペット |
8~15万円 | 8.5~18万円 |
| 畳 | 1~23万円 | 18~24万円 |
5.まとめ
フローリングの張り替えは、床材の劣化が目立つようになる約10年以降、一般的には15年~20年程度で行うことが多いようです。ただし、日頃の手入れや使い方、気候などによって大きく変動します。
また、業者を決める場合は必ず複数の業者から相見積りをとって、工事内容や工期、費用を確認してしっかり納得し、信頼できる業者にリフォームを頼みましょう。
(床・フローリングリフォームの関連記事)
全ノウハウまとめ
フローリングの張り替えを成功させる全ノウハウまとめ
その他関連記事
- 【マンションの床リフォーム】張り替え前の注意事項|工法・種類・費用を確認
- 内装フルリフォームの費用は?パターン別・築年数別の相場も解説
- キッチンの床はタイルでおしゃれに!リフォームの注意点と対策
- トイレの床材選びに悩んだら!床材の特徴・費用相場・事例を紹介
- 床下暖房(床下エアコン)とは|床暖房より経済的?メリット・注意点を確認
- 畳をフローリングにリフォームするには?費用と注意点
- 床暖房の後付けリフォーム費用や注意点、2種類の床暖房比較!
- 床の張替え費用はいくら?フローリング・クッションフロア等床材別にくわしく解説!
- フローリングの種類を徹底解説|自分好みのフローリングを選ぼう!
- 20畳のフローリング張り替えにかかる費用・コストダウンの方法も解説
床・フローリングリフォームの費用と相場